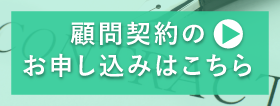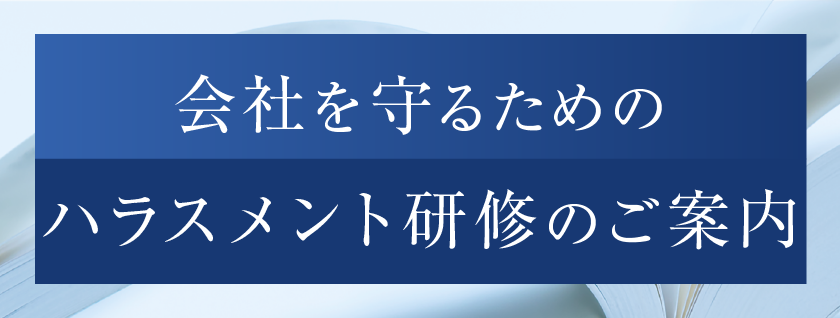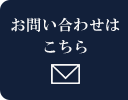2023.12.20
過労死について考える(弁護士:薄田 真司)
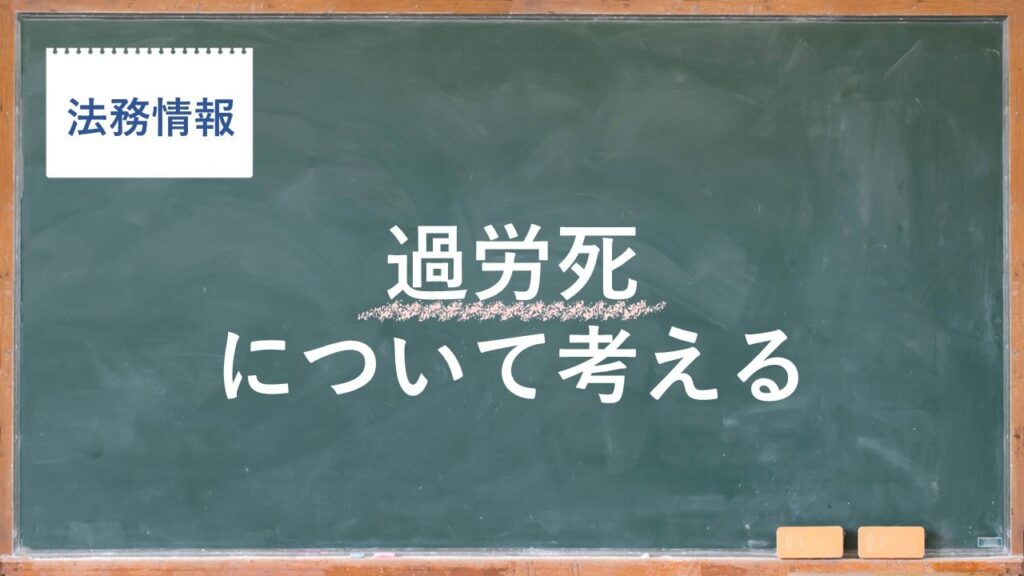
勤務医が死亡した事案について
神戸市東灘区の病院である甲南医療センターで勤務していた26 歳の医師(男性)が令和4年5 月に自殺し、本年6月に労働基準監督署が労災と認定しました。男性医師は、令和2年4月から臨床研修医として病院に勤務し、令和4 年4 月から消化器内科の専攻医(旧後期研修医)として研修を受けながら診療に従事していました。
報道によると、男性医師は、自殺までの約3か月間休暇がなく、タイムカードをもとにした男性医師の令和4年4月の時間外労働時間は約197時間、亡くなった同年5月は約133時間に上ります。
また、労働基準監督署は、専攻医になったばかりで先輩医師と同等の業務量を割り当てられ、指示された学会発表の準備も重なり、長時間労働となり、精神障害を発症したことが自殺の原因となったとしています。
これに対し、病院の院長は本年8月17日に記者会見し、「病院にいた時間が全て労働時間ではなく、自主学習や睡眠の時間も含まれ、切り分けは難しい。上司らの意見などから、過重な労働の負荷があったとは認識していない」と説明しています。
また、病院は、労働基準監督署が認定した労働時間に基づき、未払となっていた残業代を遺族に支払ったとのことです。
今回の労災事件も長時間労働が原因となっている可能性は否定できず、過労死事案の一つといえると思われます。
過労死防止に関するガイドラインについて
過労死とは、「業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡」をいい、「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」もこれに含まれるとされます。
また、脳・心臓疾患にかかる労災認定基準においては、週40時間を超える時間外・休日労働が概ね月45時間を超えて長くなるほど、業務とそれらの発症との関連性が徐々に強まり、「発症前1 か月間に概ね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たり概ね80時間を超える時間外・休日労働」(一般に「過労死ライン」と呼ばれています。)が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
加えて、業務における強い心理的負荷による精神障害で、正常な認識、行為選択能力や自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害され、自殺に至る場合があるとされています(以上につき、厚生労働省『過労死等を防止するための対策BOOK』)。
そうすると、本件の男性医師の時間外労働時間は過労死ラインを著しく超えており、それが原因で精神障害となり自殺に至ったのではないか、と推測しうるところです。
国は、「過労死等防止のための対策に関する大綱の数値目標」(令和3年7月変更)を定めています。
具体的には、①週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下にする(令和7年まで)、②勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を5%未満、制度を導入している企業割合を15%以上にする(令和7年まで)、③年次有給休暇の取得率を70%以上にする(令和7年まで)、④メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にする(令和4年まで)等です。
各職場の実態に即した形でワークライフバランスを実現し、職場の生産性を高められるよう、労使間・労働者間で協力していければと思います。
医師の自己研鑽について

本件で病院の院長も述べていますが、医師が自身の研鑽に充てた時間が労働時間といえるかが問題となる場合があります。
厚生労働省は概ね次のとおりまとめています(厚生労働省「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」)。
まず、所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所(院内等)において研鑽を行う場合は、当然に労働時間となるとしています。
これに対し、所定労働時間外に行う医師の研鑽は、上司による明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行う場合でも一般的に労働時間とはならず、逆に上司の指示によって行われるものである場合には、診療等の本来業務との直接の関連性がないものでも、一般的に労働時間となるとしています。
また、「事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続及び環境の整備」として、特に労働に該当しない研鑽を行うために在院する医師の取扱いにつき、当該医師を診療体制には含めない、勤務場所とは別に研鑽を行う場所を設ける、白衣を着用せずに行うこととする等、通常勤務ではないことが外形的に明確に見分けられる措置を講じること、その取扱いを書面等で示したうえ、医師以外の他の職種も含む院内職員に周知すること等が示されています。
これらの指摘は、美容師等の専門職領域にも当てはまりうると思います。
本件ではこれらの取扱いがなされていたのかどうかが問われ得ると思います。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2023年10月5日号(vol.285)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。


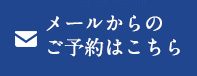

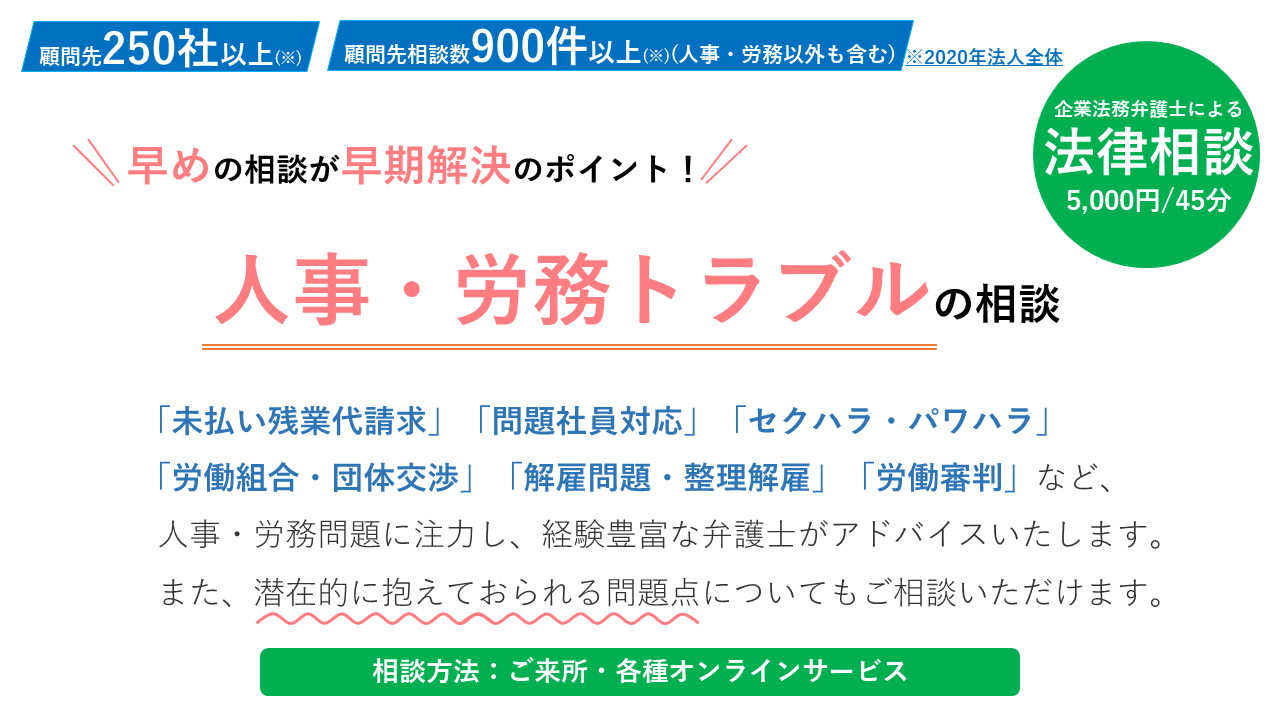
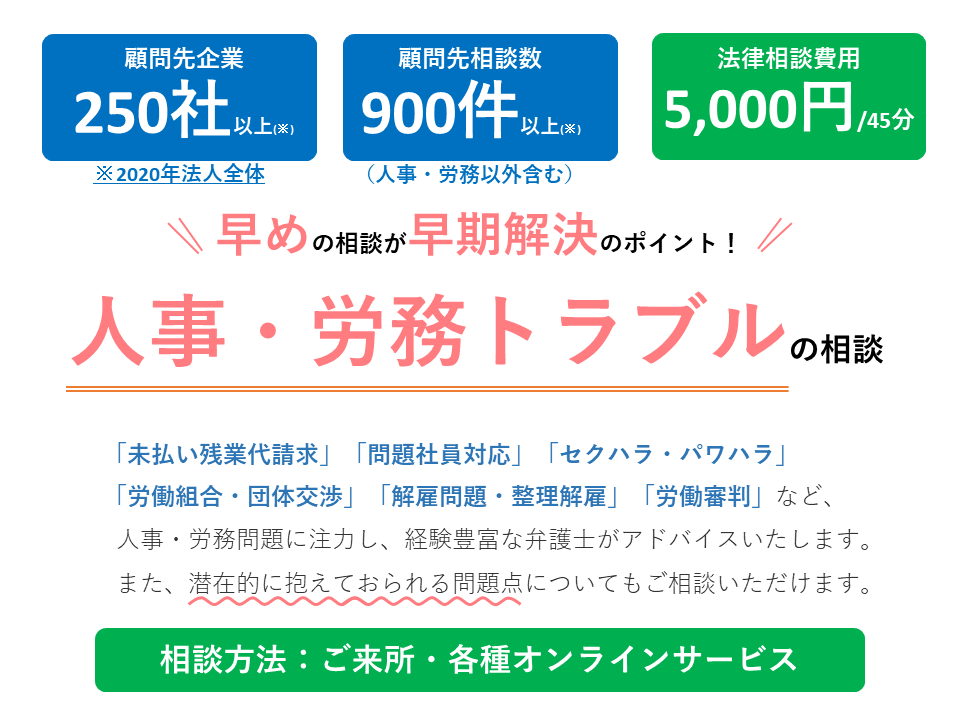
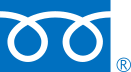 法律相談予約
法律相談予約