2025.4.9
手段としてのNDA
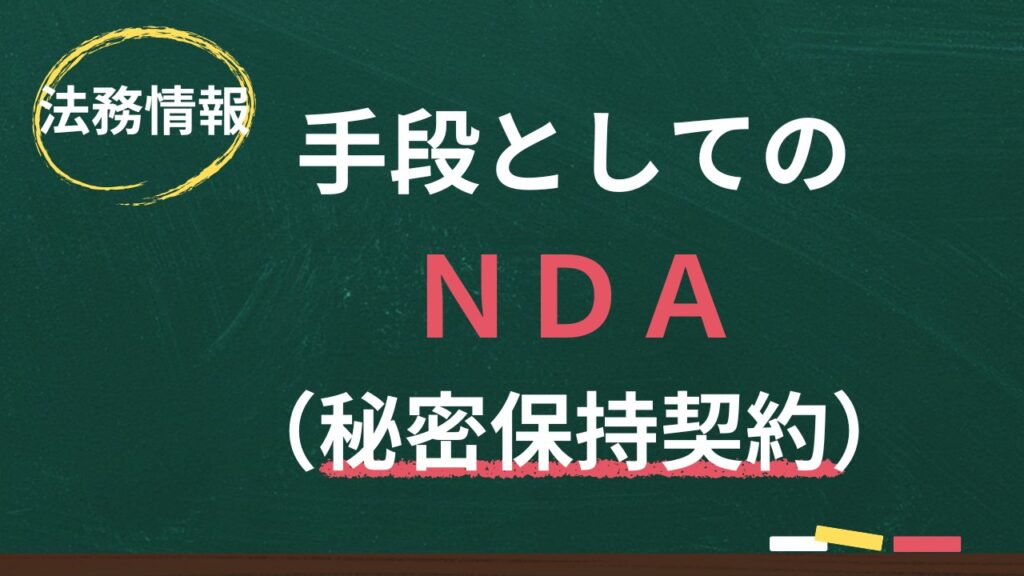
はじめに
秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement,以下「NDA」と表記します。)はビジネスの入り口として重要な役割を担っている契約類型です。
もっとも、内容をよく把握せずに自社で利用する定型的なひな型文書を交わすのみであれば、大きなコストをかけ、大きな責任を負って営業秘密のやりとりをする意義が薄れてしまいます。
本稿では、そんなNDAを基礎から振り返り、取引の相手方を選択する「手段としてのNDA」の理解を深めていければと考えています。
NDAの目的
まず、何のためにNDAを締結するかという点を再確認しましょう。
端的に言えば、NDAは今後共同して研究・開発をしていく取引相手の選定するために締結するものとなります。
取引相手を選定するためには、互いの営業秘密を開示し合い、互いの研究がどこまで進んでいるのか等の情報のやりとりをし、今後の展望を検討することはビジネスの発展のために有用な手段です。
もっとも、営業秘密は企業にとって代え難いものであり、一度外部に流出してしまえば完全な損害の回復は不可能です。
そのためにNDAを締結し、互いに開示する情報の秘密保持を誓約させることで可及的に情報流出のリスクを排除し、万が一流出があった場合の責任を明確にしておくこととなります。
NDAで規定される内容
開示側は、営業秘密流出のリスクを回避すべく、相手方に厳格に情報管理の義務を課すことが望ましいです。
反面、受領側としては、情報管理の時間とコストを削減し、競業他社から遅れを取らないためにも、なるべく軽い管理義務を定めたいところです。
このような双方の思惑を踏まえ、NDAの規定内容を決定していくことになります。
【1】情報の利用目的
開示側としても受領側としても、まずはどのような目的で情報の開示がなされるのかを具体的に定めておかなければ、安心して情報のやりとりをすることができません。
特に開示側としては、開示した情報の目的外利用を排除できなければ、営業秘密流出のリスクが格段に高まることと
なります。
受領側にとっても、情報利用目的が情報管理の大きな指標となります。
そのため、目指す成果がどのようなものなのかを具体的に確認したうえ、どのような情報をどのような研究開発のために利用するか等、情報利用の目的を定める必要があります。
【2】秘密保持の対象、情報の開示・管理態様についての規定
情報の開示方法・管理方法の規定も営業秘密を守るうえで重要なものとなります。
開示・管理の方法としては、オンラインストレージ上での情報共有が考えられます。
営業秘密について、「社外秘」「Confidential」といった表示をし、秘密保持の対象であることを明確にしつつ、開示するファイルにアクセスできる人間を限定し、アクセスのためのパスワード等を管理させるという態様です。
開示側は不用意にデータや現物を相手方に渡さず済み、アクセスできる人間を限定するため、受領側の管理態様をコントロールすることができます。
受領側も、管理すべき事項が明白で限定的になることでその分管理コストが抑えられます。
【3】義務違反の場合の損害賠償の予定
万が一、営業秘密の流出があった場合、受領側がどのような責任を負うかという点も重要な規定となります。
まだビジネスとして成立する前段階の情報に関する損害であるため、損害額をどのように算定評価し立証するのかという点は困難な問題です。
そのため、義務違反があった場合の損害賠償額の予定額を定めておき、損害の立証や損害評価の困難性を予め排除することが一つの備えとなります。
【4】その他の留意点
上記の他にも、既に自社で持っている情報を開示された場合(コンタミネーションリスク)の手当てや、契約当事者間の力関係が大きい場合の締結交渉、外国法が絡む場合の配慮等、注意すべき場面は数多くあり具体的なケースに基づいて検討を要することになります。
さらに、N D A 締結後は、開示側は受領側の管理態様を把握し、受領側は実際に営業秘密の管理をしていく必要があるため、万が一の責任・損害を負わないためにも繊細な対応が求められます。
NDAの必要性に関する検討
上記のように、ビジネスの発展のために有用に思えるNDAですが、現在ではむやみにNDAを締結しない方針を採る企業も増えてきているものとも耳にします。
というのも、N D Aに規定される情報管理のコストや責任が非常に重くなることが多いためです。
NDAの締結が相手方選定のための手段に過ぎない点を踏まえれば、営業秘密の開示以外の方法に代替できるのであればそれに越したことはないのです。
営業秘密の流出被害が不可逆的なものであることは前述のとおりであり、そのような被害を防ぐには情報を第三者に開示しないことがもっとも効果的です。
したがって、まずは営業秘密の開示なしに相手方の選定を進められないかという点を検討する意義は大いにあります。
あくまで契約相手方選定の「手段としてのN D A 」だということを、頭の隅にでも置いておく必要があるものと考えます。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年2月5日号(vol.300)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。




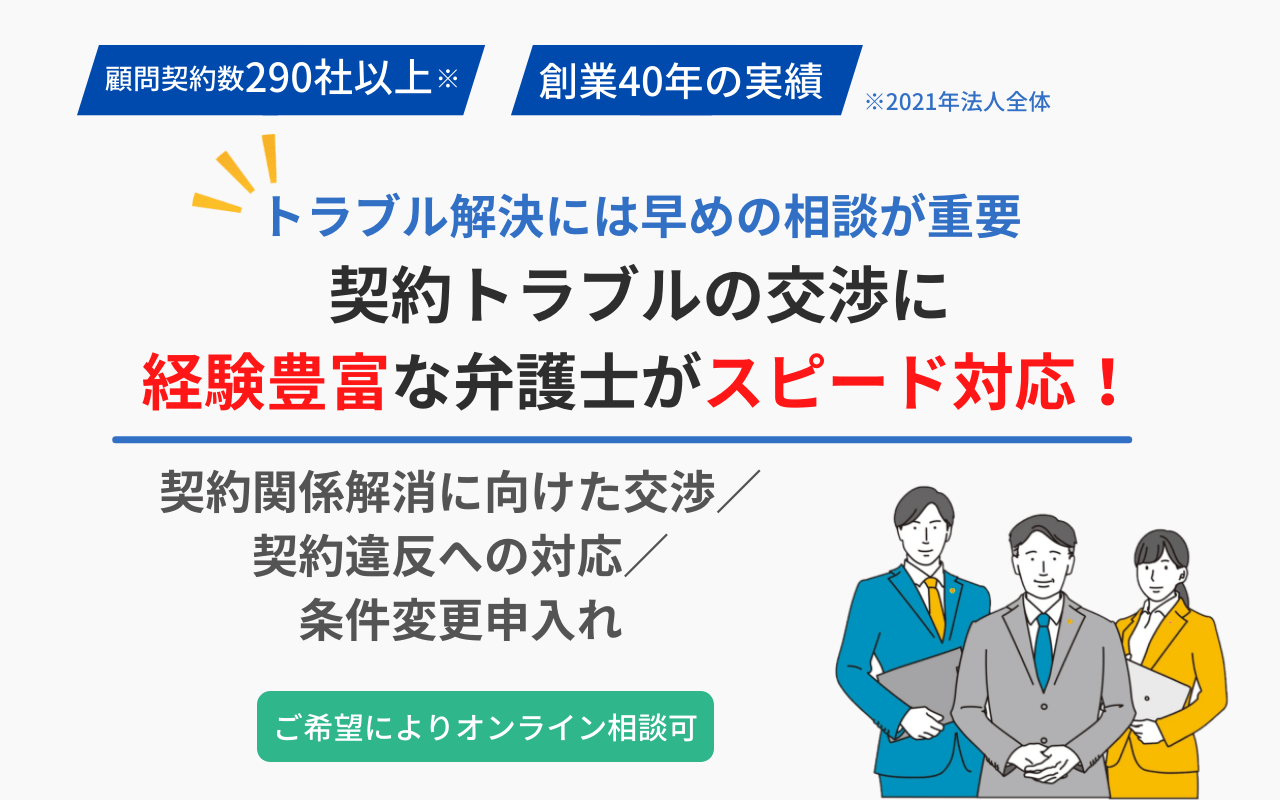
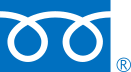 法律相談予約
法律相談予約










