2025.7.15
契約書レビューにおける弁護士の視点
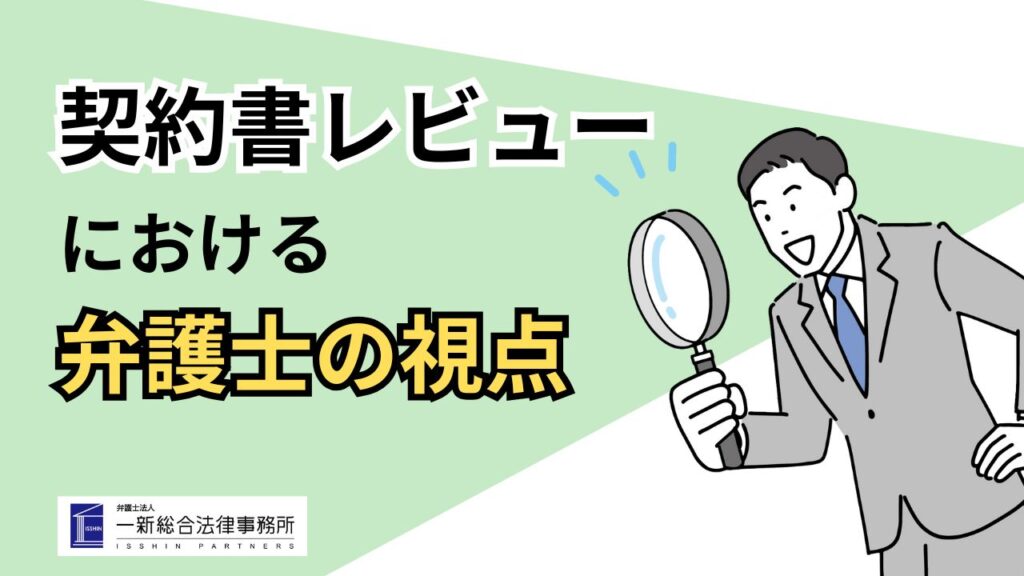
はじめに
ビジネスの場面では、契約書の取り交わしをすることは少なくなく、その際、契約内容がこの内容で問題ないのか疑問を持つこともあるかと思われます。
本稿では、建物や土地の賃貸借契約を例示として挙げながら、弁護士が契約書のレビューを行う際の視点をいくつか、紹介したいと思います。
契約書レビューにおける着眼点
【1】民法等の法律や標準契約等との比較
まずは、民法などの法律と異なる点がないかを確認します。
契約内容が有利か不利かを判断する際の視点の一つは、このよう民法等の法律の規定との比較になります。
また、実際に違反等があることは少ないものの、法令等や強行規定(当事者が当該規定と異なる合意をしても、その合意は無効となり当該規定が適用されるもの)に反しないかなども確認します。
例えば、借地借家法では、建物所有を目的とする土地の賃借権等の存続期間などに関して、借地借家法の規定に反する特約で借主に不利なものは無効としています(借地借家法9条)。
そのため、建物所有を目的とする賃貸借契約の場合、契約期間を2 0 年間と定めたとしても、その合意は無効とされ、法律に規定された30年間(借地借家法3条)となります。
また、公的機関などによって契約書の例が公開されていることもあり、このような公的機関の契約書と比較することもあります。
賃貸借契約書に関連するものでは、国土交通省から、賃貸住宅標準契約書や定期賃貸住宅標準契約書等が公開されています。
なお、法律や標準的な契約書との比較の結果、自社にとって不利であったとしても、必ずしも修正を求めるわけではありません。
例えば、賃料の支払時期に関しては、民法では、後払い(当月分をその月末に支払う)とされています( 民法6 1 4 条)。
しかし、一般的には、前払い(翌月分を前月末日までに支払う)ことが多いかと思われ、賃貸住宅標準契約書上も、後払いか先払いかを選択する形式になっています。
そのため、先払いでも特段支障がなければ、修正を求めないこともあり得ます。
【2】相手方との関係性
どの程度修正の要望を出すかにあたっては、契約相手との関係性が重要となります。
こちらの立場が強い(相手方と契約を締結しなくても不利益が少なく、一方、相手方は契約締結を強く希望している等)のであれば、相手方が契約自体を拒否する可能性は低いため、より有利な内容となるよう修正要望を出していくことも考えられます。
逆に、こちらの立場が弱い場合、修正要望を出しすぎてしまうと契約自体を拒否されてしまうおそれもあることから、契約の締結を優先し、修正要望は最低限にとどめることも考えられます。
例えば、建物の賃貸借契約において、損害賠償に関する定めとして、借主が明渡しを遅滞した場合、「契約終了から明渡しが完了するまでの間、賃料の倍額に相当する損害金を支払う」のような規定があったとします。
法律上、明渡しの遅滞による損害賠償は賃料相当額で足りるため、この規定は、借主に不利なものといえますが、あくまでも明渡しを遅滞した際のものであって、期限内の明渡しができれば、損害賠償義務は負わないことなります。
そのため、借主の立場であっても、この規定の修正等は求めず、契約終了時に、期限内に明渡しができるよう余裕をもって準備する等の対応をすることも考えられます。
このように、修正の要望をしない場合には、自社にとって不利であることや問題が生じるリスクがあることを理解し、その問題等が生じない、または、最小限に抑えられるよう備えておくことが重要となってきます。
【3】契約の目的・趣旨等
契約の締結にあたっては、何らかの目的・趣旨等があるかと思われますので、それを確認したうえ、そのような目的が実現可能なものかなども検討します。
賃貸借契約においても、建物や土地を自社で利用するのか、第三者への転貸を予定しているのか等によって、契約内容は自ずと変化するものと思われます。
例えば、民法では、転貸をするには、賃貸人の承諾が必要とされています( 民法6 1 2 条1項)ので、契約書上で事前に転貸の承諾する旨の規定を設けておくことが考えられます。
また、賃貸する建物を、将来的に利用する予定がある場合に、通常の建物賃貸借契約を締結してしまうと、期間満了により契約を終了しようとしても、正当事由(借地借家法28条)の有無で争いになる可能性もあります。
そこで、このような場合には、契約締結の段階で、定期建物賃貸借を利用することも検討すべきです。
【4】表記の統一
契約書において、本来同じものを指しているのに異なる表記を用いてしまうと、後に、同一のものを指しているのか、疑義が生じる場合もあります。
例えば、賃貸借の対象となる建物について「本件建物」と定義したにもかかわらず、「本建物」等の別の表現を用いてしまうと、賃貸借の対象とした建物を指しているのか、判然としなくなってしまうおそれもあります。
したがって、契約書上の文言や表記等は統一するよう意識する必要があります。
おわりに
本稿では、弁護士が契約書レビューをする際の視点について、いくつかご紹介させていただきました。
契約書は、事後的にトラブルになった際にも必ずと言っていいほど確認するものですので、トラブルの予防や万が一の場合の対応のためにも、きちんとしたものを作成すべきといえます。
もし契約の締結等にあたって、契約内容にご不安な点などがありましたら、何なりと当事務所にご相談いただけますと幸いです。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年5月5日号(vol.303)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。




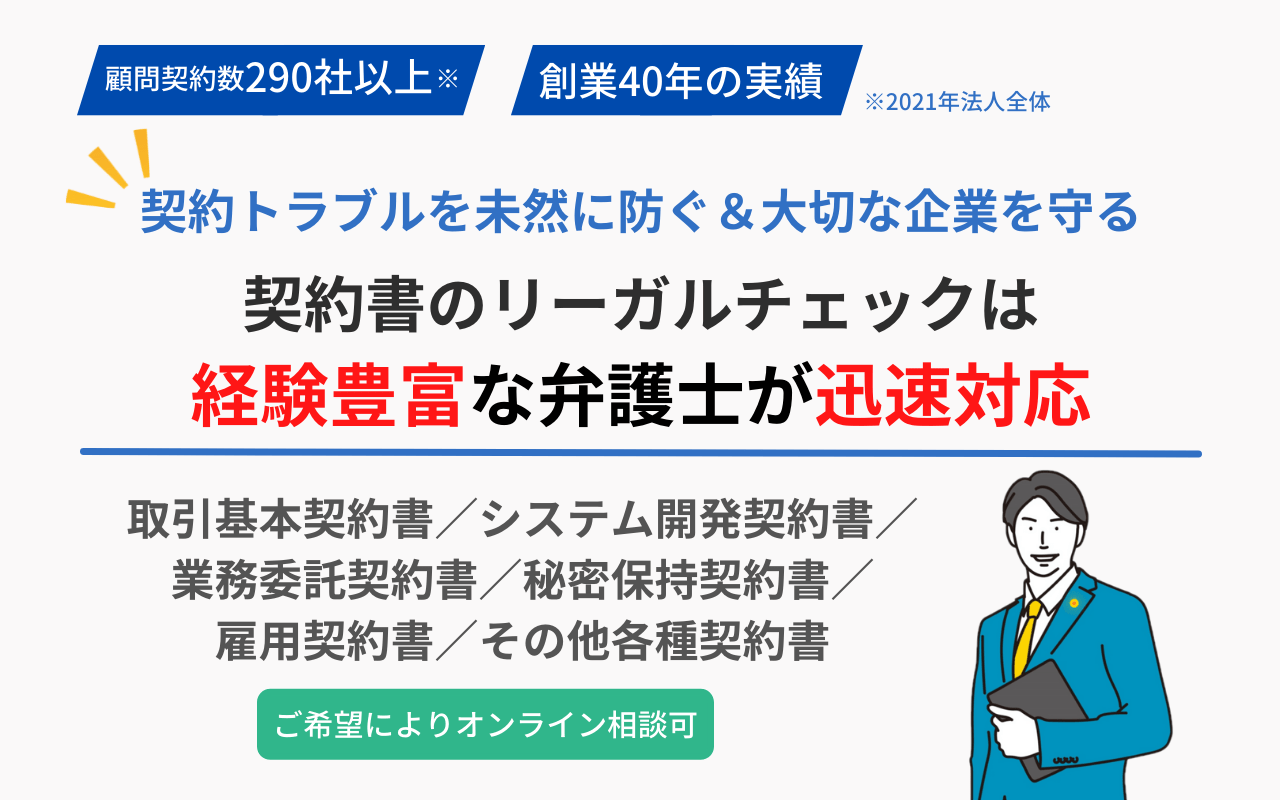
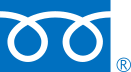 法律相談予約
法律相談予約










