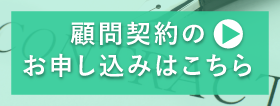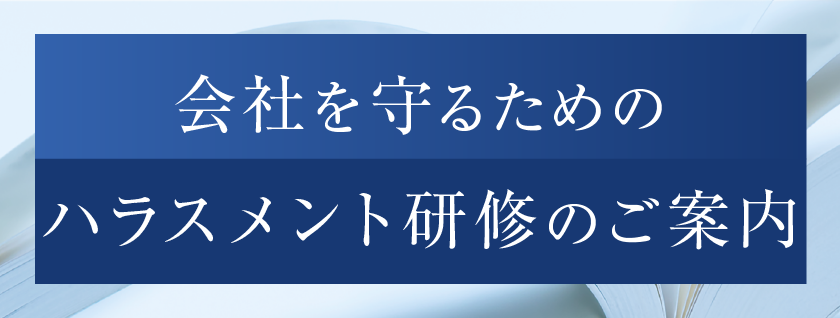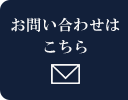2023.7.11
消費者契約法改正(弁護士:下山田 聖)

消費者契約法は、消費者が事業者と契約をする際に、持っている情報や交渉力に差があることを踏まえて、消費者の利益を保護するための法律です。
平成13年4月1日に施行された後、複数回の改正を経て、現在に至っています。
この度、令和4年12月10日に消費者法の改正法案が成立し、令和5年6月1日から施行(一部条文については令和5年10月1日から施行)されることとなりましたので、改正点を解説します。
契約の取消権の追加(4条3項)
まず、一定の場合に、消費者が契約を取り消すことができると規定されました。
「無効」と「取消し」は、当該行為がさかのぼって効力を生じないこととなる点では同じですが、「無効」の場合には特にアクションは不要であるのに対し、「取消し」は、取消権者が取消権を行使してはじめて効力を失う、という違いがあります。
消費者契約法の改正で追加された取消権発生事由は、①勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行して勧誘した場合、②消費者を威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害した場合、③契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にした場合です。
勧誘目的を秘して事業者の事務所に連れて行ったり(上記①)、消費者が外部との連絡を希望した場合にこれを高圧的に妨害したり(上記②)した場合には、その後に契約を結んだとしても、事後的に取消権行使の対象になります。

契約終了に伴う清算に関する説明義務(努力義務)
⑴ 契約類型によっては、解除した場合の損害賠償や違約金の支払につき、予め決められているケースもあります。
これらの条項を契約書に盛り込むこと自体は特に問題ありませんが、不当に高額な違約金等が設定されているケースもあります。
今回の改正では、消費者から違約金の算出根拠の問合せを受けたときは、これに応じるよう努力しなければならない、として、事業者側の説明義務が規定されました。
これは、違約金の発生はやむを得ないとしても、算出根拠が不明確な金額だということになると、消費者としてはその額が適正かどうかを判断することができないので、そのような事態を防止するという趣旨であるものと思われます。
⑵ 「努力義務」というのは、字義通り「努力することを義務付ける」ものであり法的拘束力はありませんが、事業者側に適正な違約金等の設定を促す効果があるともいえます。
免責範囲が不明確な条項の無効
⑴ 契約を締結するに当たって、事業者の契約違反(債務不履行)があった場合に、事業者は責任を負わないという免責特約が付されていることもあります。
⑵ 改正前の消費者契約法第8 条1 項各号においても、①事業者の責任の全部を免責する特約、②事業者の債務不履行に故意又は重大な過失がある場合に、その責任の一部を免除する特約、③事業者の不法行為に基づく責任の全部を免除する特約、④事業者の不法行為に故意又は重大な過失がある場合に、その責任の一部を免除する特約は、それぞれ「無効とする」とされていました。
そうすると、改正前の消費者契約法上は、上記①から④に当てはまらない免責条項、すなわち⑤「事業者の債務不履行・不法行為に、事業者の故意又は重大な過失がない場合に、その責任の一部を免除する特約」は有効、ということになります。
⑶ 今回の改正では、消費者契約法8条に第3項が追加されました。
⑤の場合の規律を定めたものですが、当該免責条項について、「事業者……の重大な過失を除く行為にのみ適用されることを明らかにしていない条項」も「無効」ということになりました。
これは、従来の免責条項に関する規定を維持しつつ、免責条項が適用される範囲が不明確なものについても「無効」とすることで、消費者の予測可能性を確保するための規律であるといえます。
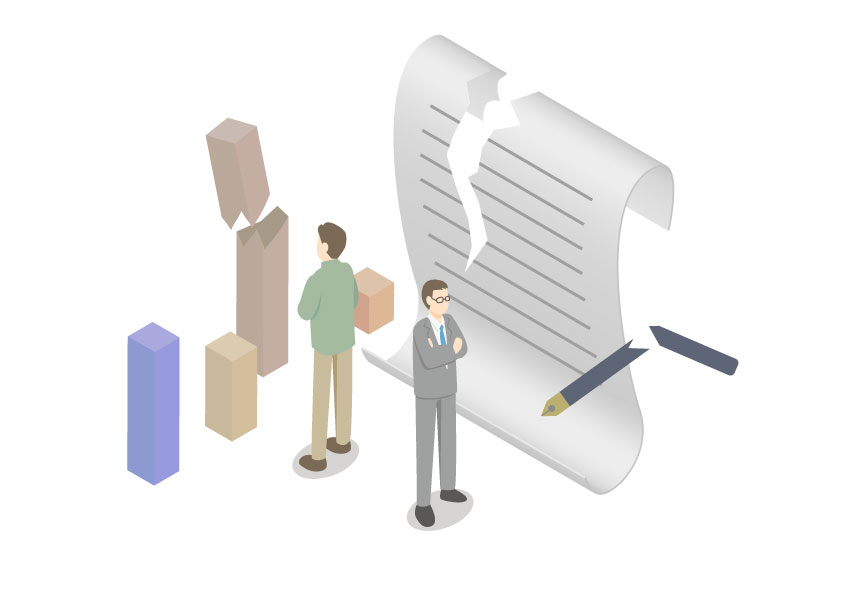
事業者の努力義務の拡大
⑴ 消費者契約法による保護がなされるといっても、消費者自身がそのことを知らなければ、結果的に利益保護が達成されないことになってしまいます。
そのような事態を避けるため、改正消費者契約法では、一定の局面における事業者側の努力義務を拡大し、消費者の利益保護を図っています。
⑵ 例えば、旧法下では、契約の「締結」時点で必要な情報を提供することが努力義務として定められていましたが、改正法では、「解除権の行使」に関しても必要な情報を提供することを努力義務としています。
また、提供すべき情報の内容についても、旧法下では「個々の消費者の知識及び経験」を考慮するとされていたのに対し、改正法では「事業者が知ることのできた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験」を考慮することとされています。
その結果、事業者側においては、より丁寧に消費者の状況を把握した上で、情報提供することが求められます。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2023年5月5日号(vol.280)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。


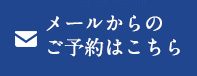

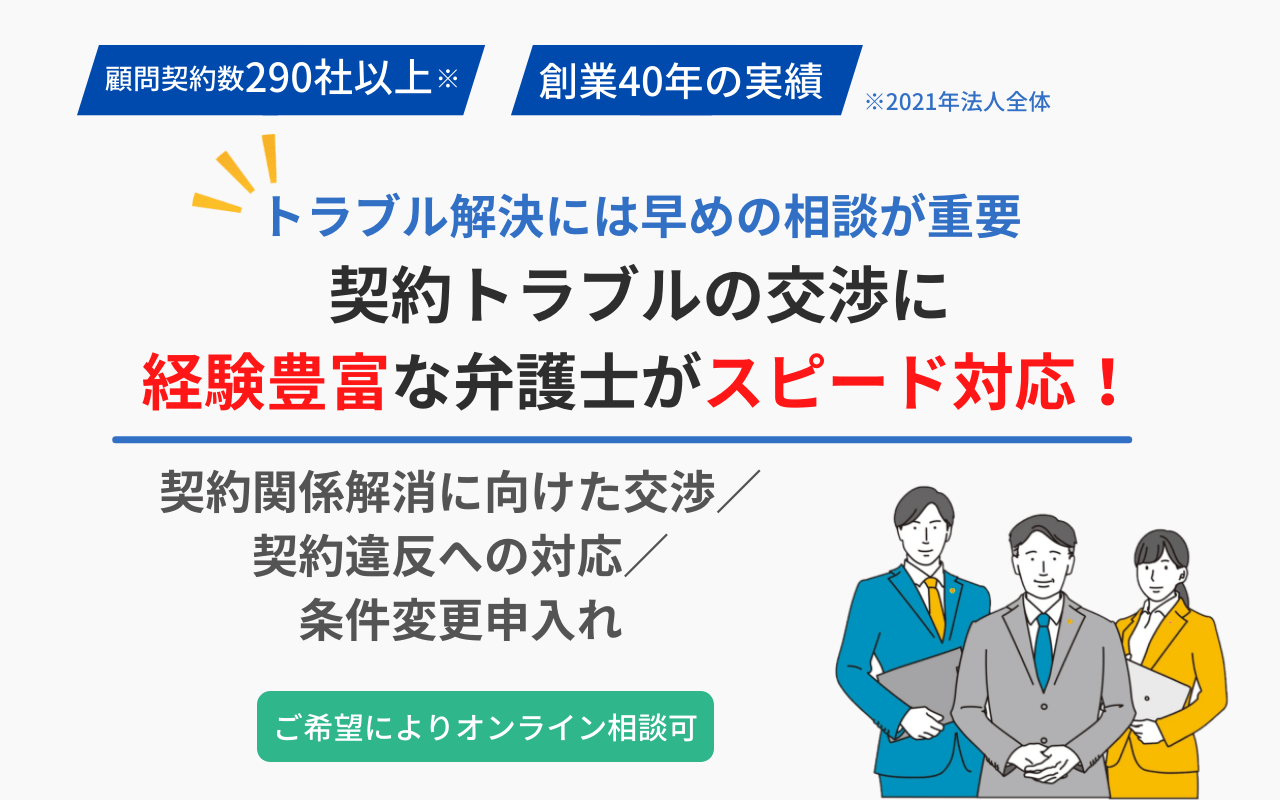
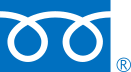 法律相談予約
法律相談予約