2025.9.5
効果的なコンプライアンス
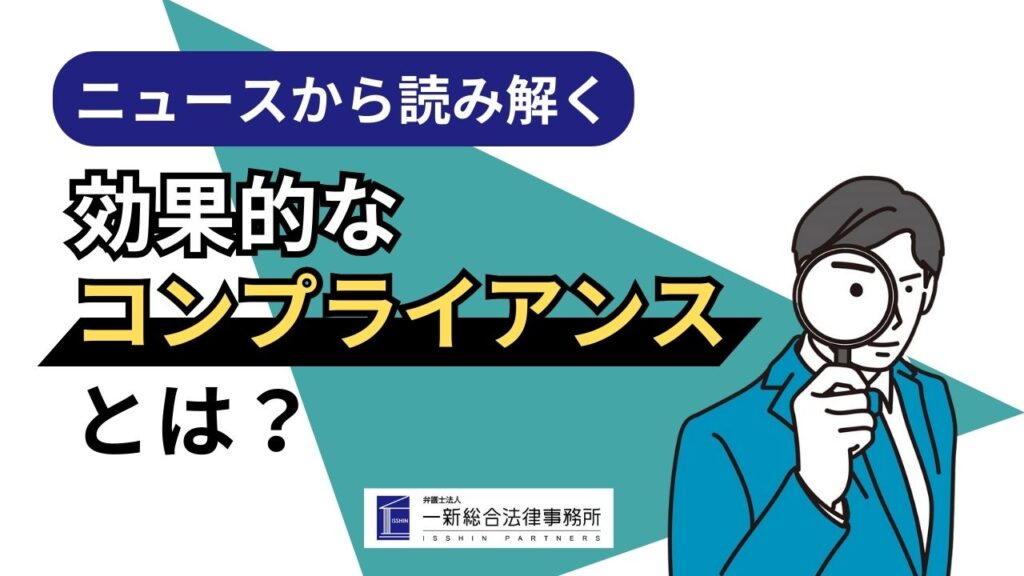
コンプライアンス
「コンプライアンス」とは、特に、企業活動において社会規範に反することなく、公正・公平に業務遂行することを意味します。
近年では、規範整備は完了し、研修も行われている企業も多いと思います。
しかし、それらが実践されている企業でも不祥事の発生を防げなかった例は多くあります。
折角の機会ですので、近時話題となったフジテレビの実例を分析してみたいと思います。
事案
男性タレントと女性社員との間に性的トラブルがあり、被害申告がなされたにもかかわらず適切な対応をとらず、被害女性(以下「被害者」といいます。)は職場復帰を希望していましたが、断念して退職せざるを得なかった事案です。
【1】初期対応
職場、及び産業医らは、被害者から被害申告を受け、被害者の心身の状況を考慮し、業務遂行及び情報共有範囲について当面の希望を確認しながら、連携して医療的支援・心理的支援を行った。
この点、第三者委員会(以下「第三者委」といいます。)から「(被害者)のプライバシーの保護と心身のケアを最優先として適切に対応を進めたものといえる」と評価されています。
【2】社長らの対応
本件事案は、被害者の入院直後に上司に報告され、約1ヵ月半後には社長にも報告されたが、「プライベートな男女間のトラブル」と即断した。
【3】対応方針
社長らは「(被害者)の生命を最優先にする、笑顔で番組に復帰するまで何もしない」という「大方針」を決定し、男性タレントの番組出演を継続させた。
【4】第三者委の見解
本事案を男性タレントと被害者が業務上の人間関係であること及び外部で会合をする業務態勢であったことなどから「業務の延長線上」で発生した「取引先から社員に対する人権侵害であるため、カスタマーハラスメント」として位置づけています。
そして、旧ジャニーズ事務所問題を契機としてスポンサーや株主などのステークホルダーの人権意識が高まっていたことから、本件事案は社会的関心を呼び、経営に大きな影響を与えることが予想されました。
情報漏洩により被害者に二次被害を与えるリスクも生じえますが、他方、情報を隠蔽したままで男性タレントの番組出演を継続させることは、視聴者、スポンサー、株主・投資家などステークホルダーらを騙すことを意味し、テレビ局の信頼が失われ、非難を浴びる可能性が高かったと指摘しています。
問題点
【1】経営判断における問題
第三者委は、「経営判断の原則」を参考とします。
①経営判断の前提となる事実認識の過程(情報収集とその分析・検討)と②事実認定に基づく意思決定の推論過程及び内容の著しい不合理さの存否という2点を意識しながら経営判断を行うことが適切であり、とりわけ①が大事となります。
この点、被害者、男性タレント及び本件事案に関連するテレビ局関係者からのヒアリングを実施して情報収集を行い、その結果に基づいて本事案への対応におけるリスクの特定、分析、検討を行った上で対応方針を決定する必要がありますが、社長らはこれらの対応を全く行いませんでした。
【2】意思決定の閉鎖性
ア
本件事案の対応方針、被害者への対応、男性タレントの出演継続の是非に関する意思決定は編成ラインのトップ3の社長を含む3人のみで行われた。
イ
被害者のケア・救済・職場復帰のためには、人事局の関与は欠かせないが、本件事案の協議から排除され、対応方針も連携されなかった。
ウ
本事案についての事実調査と人権侵害該当性の判定を担うコンプライアンス推進室長、コンプライアンス担当役員に対して本事案の情報共有・報告はなかった。
これは本事案を「編成ごと」と捉え、「ハラスメント」「人権侵害」という視点を欠いていたことによる。
エ
ビジネスと人権、ハラスメント、リスクマネジメント、PTSDを発症するような性暴力の被害者支援の専門家の助言も受けることもなかった。
オ
テレビ局にはハラスメント窓口と内部通報窓口があるが、これらは、実効性ある救済メカニズムにおいて求められる要素を満たしていなかった。
【3】テレビ局の特殊性の視点
第三者委は、以下のような付随的視点を述べています。
例えば、経営陣の意思決定の特徴として、外部に判断を仰ごうとせず、「原局主義」で独善的に物事を判断してしまう行動様式を指摘しています。
なお、その理由として、テレビ局は日々刻々と番組を制作して放送するのが日常業務であり、いちいち放送を止めてじっくり考える時間などなく、走りながら考えてどんどん現場で問題を解決して前に進めなければならない、という習慣が染みついているといった声もあったようです。
これは一見テレビ局の特殊性のようにも見えますが、業務を止めることを想定していないのはどの業種も同じであり、結局は経営陣の資質や組織の同質性・閉鎖性・硬直性の問題ともいえます。
コンプライアンスの実効性
この事案から規範整備済みのコンプライアンスに実効性を持たせるためには、以下のことが重要であることが確認できます。
❶当事者への聴き取り
❷コンプライアンス担当部署や人事局との連携
❸専門家への相談
❹人権視点に基づく意識
特に、第三者委は本事案を「カスタマーハラスメント」と位置づけているにもかかわらず、本事案を取り仕切った社長らにこのような意識が皆無であったことが事態を悪化させたともいえます。
最後に
前記事案において、ステークホルダーから直接的な批判が始まる契機となったのが第1回目の社長の記者会見であったことも忘れてはいけません。
記者会見が世間の注目を集める場であることからすれば、聞き手を納得させる準備のない記者会見はむしろ有害であることに注意すべきでしょう。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年7月5日号(vol.305)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。




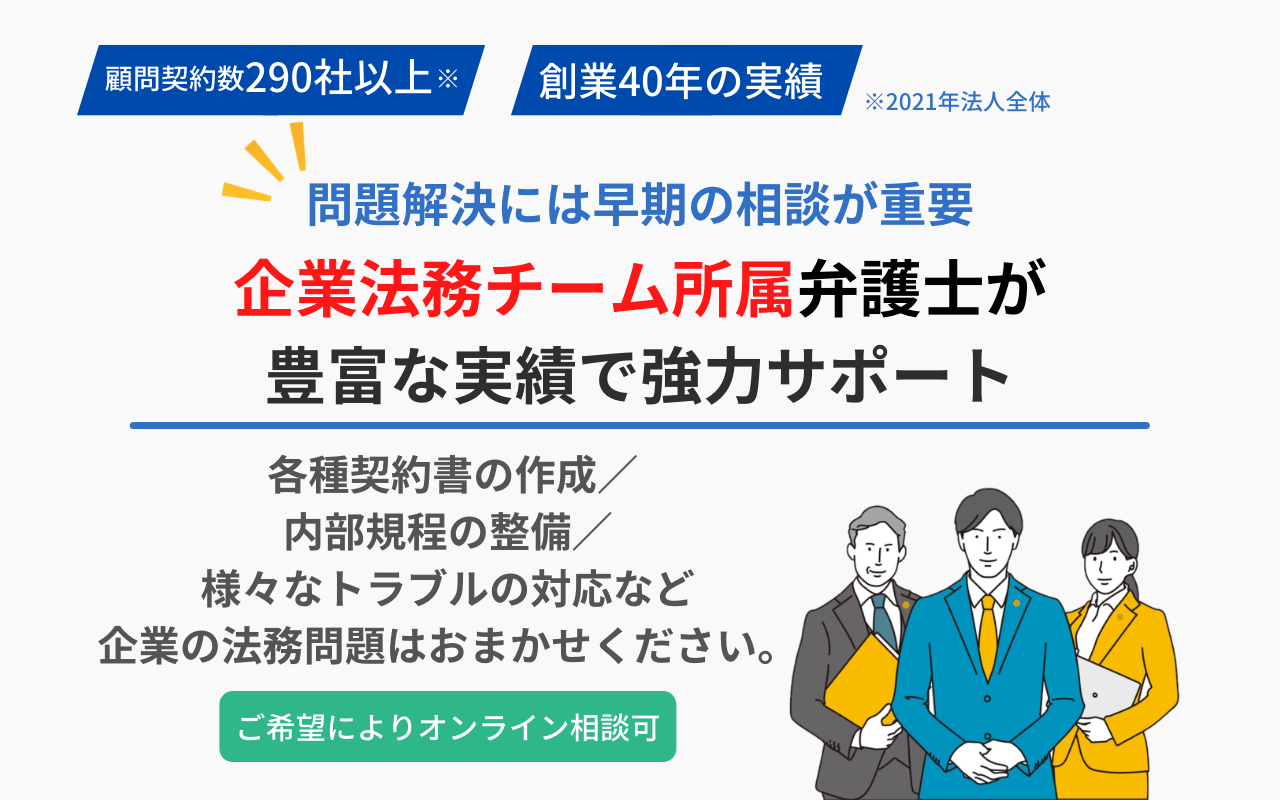
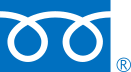 法律相談予約
法律相談予約










