2024.6.17
企業が確認しておきたい消費者契約法改正のポイント(弁護士:佐藤 明)
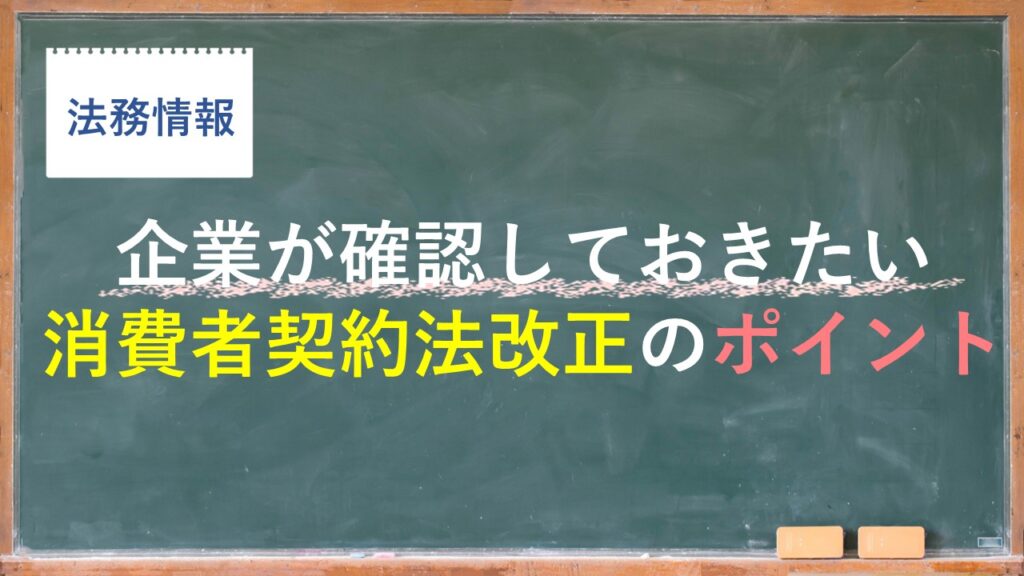
消費者契約法が令和4 年に改正され、同5年6月1日に施行されました。
消費者契約法は消費者と事業者(企業等)との間の契約(消費者契約)について知識や経験差などを考慮し消費者を保護するための法律(以下では単に法といいます。)であり、年々社会的に消費者問題が生じていることを受けてその保護の強化が図られてきています。
今回の改正も企業において消費者対応のため留意する必要がありますので、関連する改正点の概要を以下に説明します。
改正の概要
⑴ 不当勧誘による契約の取消権の追加
これまでも契約の取消権の事由として、不実告知、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害、不安をあおる告知、契約締結前の義務の実施等が規定されていました。
さらに今回は以下の場合を追加しました。
① 勧誘することを告げずに、退去困難な場所へ同行し勧誘すること(法4条3項3号)
たとえば、ドライブしようと告げて消費者を車で人里離れた場所に連れて行き商品を販売するような場合です。
② 威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害すること(法4条3項4号)
たとえば、商品を買うか親に相談したいと消費者が言ったのに、大人なんだから自分で判断すべきと相談を妨害して勧誘するような場合です。
③ 契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にすること(法4条3項9号)
たとえば、指輪の買い取りの際に指輪に付いていた宝石を鑑定するために取り外し、元に戻すことを著しく困難にして勧誘するような場合です。
⑵ 不当条項として契約無効となる場合の追加
今回の改正前は、不当条項として無効となる場合として、故意・過失の賠償責任の全部又は一部免責、軽過失の全部免責、平均的な損害の額を超える解約料などが規定されていました。
今回の改正で、消費者から事業者に対する賠償請求を困難とする不明確な一部免責条項を無効とすることとして追加しました(法8条3項)。
たとえば、事業者に故意・重過失がある場合には全額賠償が認められるのに「法律上許される限り、1 万円を限度として賠償責任を負う」旨の契約書はこれに当たり無効となります。
この場合、賠償限度を定めるとして「軽過失」の場合であることを明確にする必要があります。

⑶ 事業者の努力義務の拡充
今回の改正前には、事業者の努力義務として契約締結について加入するに際して消費者の知識・経験を考慮した情報提供などが規定されていました。
さらに今回は、次の点が拡充されました。
この努力義務は法的な義務ではないので、事業者がこれに反しても直ちに法的なペナルティが課されることはないですが、消費者保護ひいては企業の信用のためにも尊重されるべきものと考えます。
① 勧誘時の情報提供の考慮要素として年齢・心身の状態も追加(法3条1項2号)
今回の改正によって、消費者の契約勧誘に際し、契約の目的物の性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で消費者契約の内容について必要な情報を提供することが明確化されました。
② 契約締結時だけでなく解除時に努力義務を導入
今回の改正によって、解除時にも、
(ア) 事業者は、消費者から求められたら解除権の行使に必要な情報を提供するよう努めなければならない(法3条1項4号)
(イ) また事業者は、解約料を請求する際に消費者から求められたら、解約料の算定根拠の概要を説明するよう努めなければならない(法9条2項)
とされました。
③ 定型約款の表示請求権に関する情報提供(法3条1項3号)
事業者は、消費者が民法上の定形約款の表示請求権(548条の3第1項)を行使するために必要な情報を提供するよう努めなければなりません。
ただ、約款の内容を消費者が容易に知り得る措置を講じている場合(書面交付など)は除かれます。
④ 適格消費者団体の要請に対する努力義務
さらに今回の改正で、事業者は、適格消費者団体(不特定多数の消費者に代わり事業者への差止請求権を行使するため内閣総理大臣に認定された消費者団体)から、次の点を要請された場合について応じるよう努めなければならないとされました。
(ア) 不当条項と疑われる契約条項の開示(法12条の3)
(イ) 解約料の算定根拠(営業秘密は除きます。)の説明(法12条の4)
(ウ) 差止請求を受けて行った措置の内容の説明(法12条の5)
以上の改正点等につき、企業が留意すべきことはいうまでもありませんが、前述したように、努力義務については法的な強制力のある義務でないとはいえ消費者保護、企業の信用などから意識して対応することが望まれます。
なお、消費者庁のHP には豊富な関係資料が挙げられていますし、消費者向けですが「知っていますか?消費者契約法」はわかりやすく参考になります。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2024年4月5日号(vol.291)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。




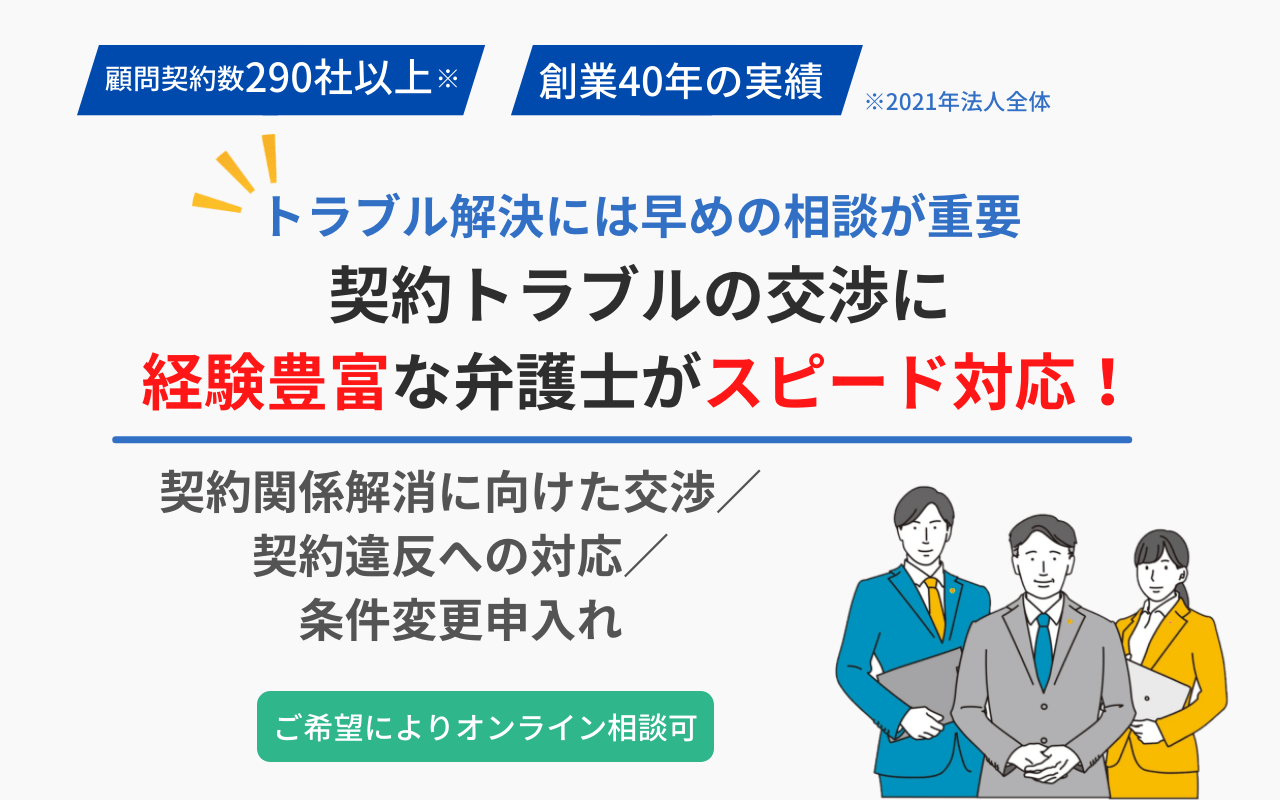
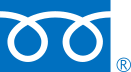 法律相談予約
法律相談予約










