2023.2.15
電子署名の裁判上の取扱い(弁護士:鈴木 孝規)
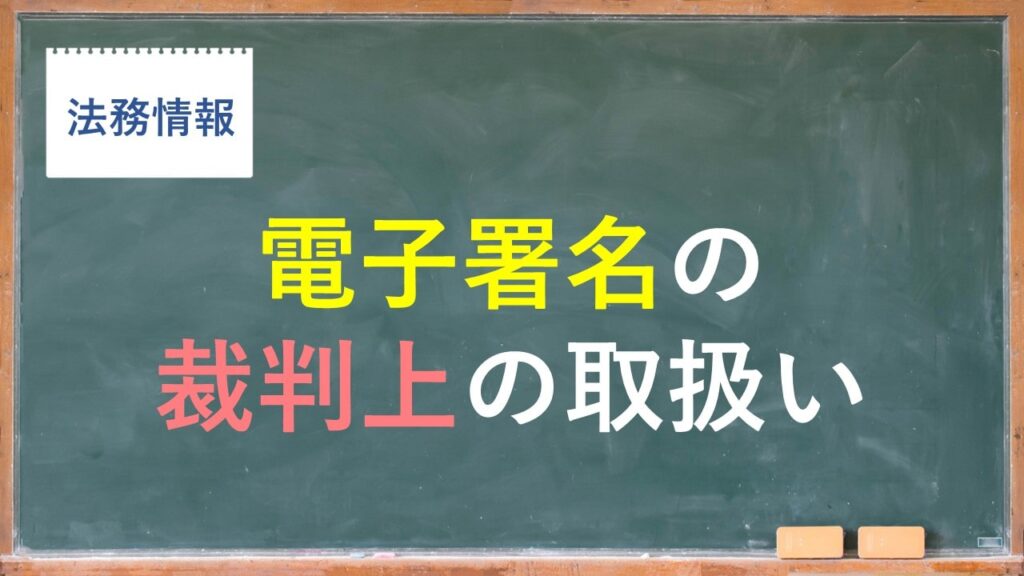
はじめに
本稿では、新型コロナウイルス感染症の影響で、利用するようになった方や利用を検討している方もいると思われる電子署名に関して、裁判上どのような扱いを受けるか、説明していきたいと思います。
紙の契約書の場合
紙の契約書の場合、本人の署名または押印があれば、真正に成立したもの(本人の意思に基づいて当該文書が作成された)と推定されます(民事訴訟法228条4項)。
民事訴訟で契約の成否が争いとなった場合、契約が成立したことで利益を受ける側がこの事実を主張・立証しなければなりませんが、契約書に本人の署名または押印さえあれば、この規定が適用され、相手方において推定を覆すことができなければ、契約が成立したものと認められます。

電子署名の場合
一方、電子署名の場合、① 電子文書に付された電子署名が、電子署名法2条1項の電子署名に該当し、かつ、「その電子署名を行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるもの」であること、② 電子署名が本人(電子文書の作成名義人)の意思に基づき行われたものであること、の要件を満たすことで、成立の真正が推定されます(電子署名法3条)。
条文の文言自体は難しいのですが、基本的には、当事者双方がそれぞれ電子署名を利用した場合には、この規定が適用されます。
また、電子署名を行う際にサービス提供事業者が自動的・機械的に利用者名義の一時的な電子署名を発行し、それに紐づく署名鍵により暗号化等を行うサービスもありますが、このようなものでも、十分な水準の固有性(他人が容易に同一のものを作成することができないと認められること)が満たされている場合には、この規定が適用されると考えられています。
例えば、2要素による認証(事前に登録したメールアドレス・パスワードとワンタイム・パスワードの入力)を行うことではじめて電子署名を利用でき、かつ、サービス提供事業者が行うシステム処理が当該利用者に紐づいて適切に行われる等、電子文書が利用者の作成したものであることを示すための措置として十分な固有性を満たしていると認められる場合です。
おわりに
契約書は、事後的なトラブルを避けるために作成している面もありますが、いつ、どのようなトラブルとなるかは予測が難しいものもあります。
仮に訴訟になった場合でも、契約の成否が争いにならなければ、文書の成立の真正を意識する必要はないのですが、トラブルの予測は困難なため、電子署名を利用する際には、推定規定の適用が受けられるかどうかを意識したほうがよいかと思われます。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2022年12月5日号(vol.275)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。




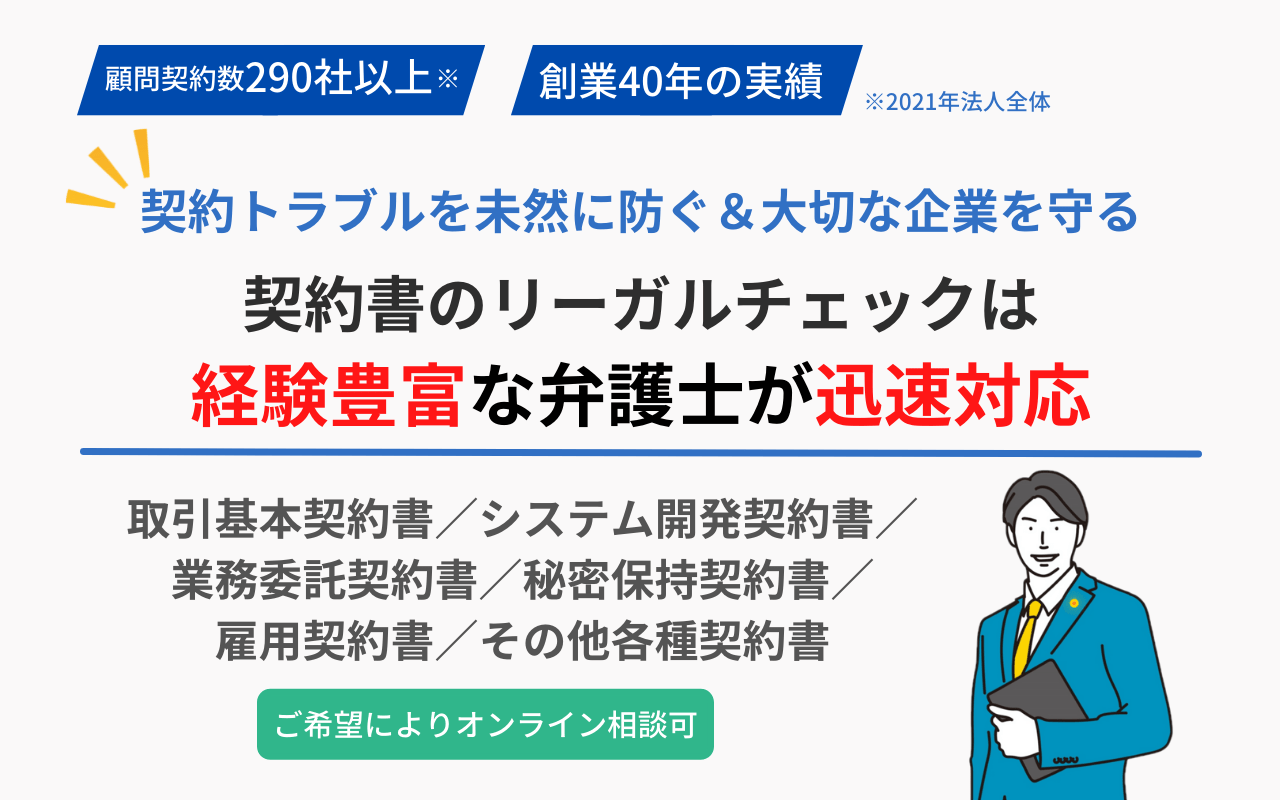
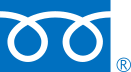 法律相談予約
法律相談予約










