2020.11.16
退職勧奨の実施方法と注意点(弁護士:五十嵐亮)
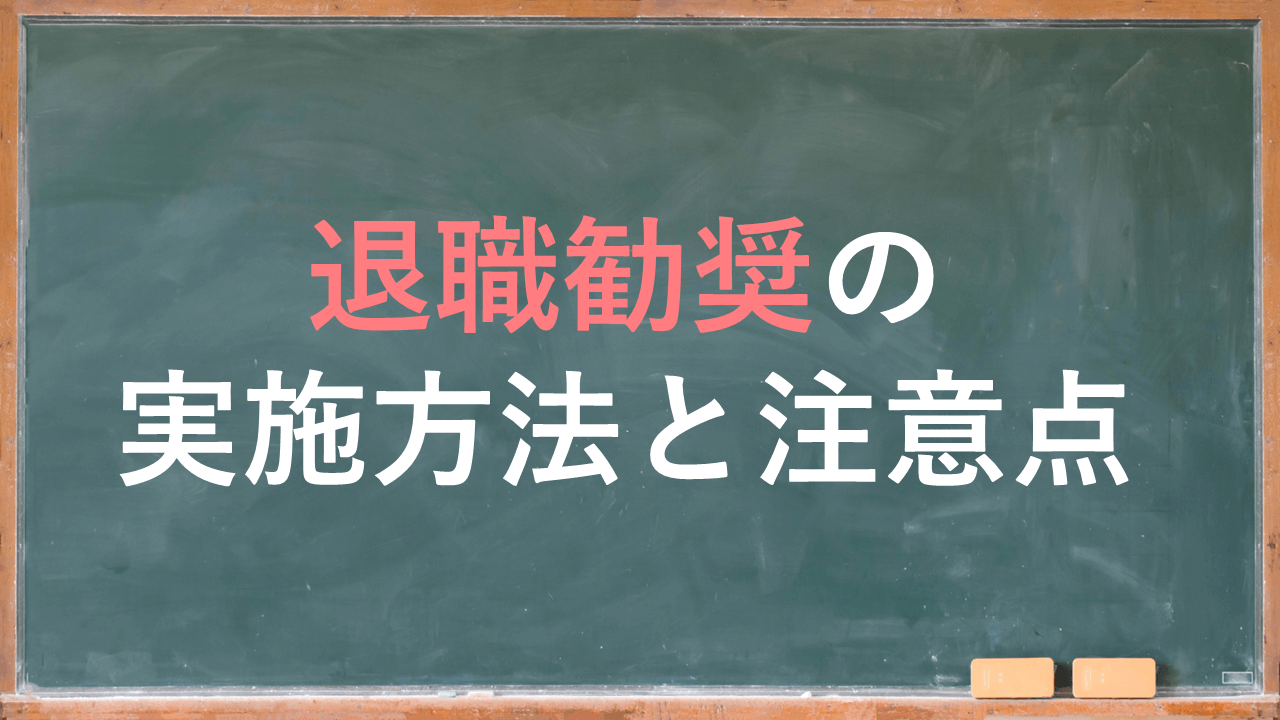
□退職勧奨とは?
コロナ禍において、企業再建の手段の一つとして、雇用調整を行わなければならない場合があると思います。
雇用調整の手段としては、①希望退職者募集、②退職勧奨、③整理解雇(リストラ)等が考えられます。
整理解雇は、訴訟・紛争リスクが高いため最終手段として位置づけられます。
他方、希望退職者募集や退職勧奨は、解雇ではなく、合意による退職なので、解雇に比して訴訟・紛争リスクが低いため、整理解雇の前に実施されることになります。
希望退職者募集と退職勧奨の違いは、前者は、従業員を特定することなく広く退職を募集するものであるのに対し、後者は、企業側が従業員を選定して勧奨する点にあります。
そのような性質から、退職勧奨は、人事評価や成績が低い従業員を選定して実施されることが多いといえます。
□退職勧奨の方法

退職勧奨は、文字取り、企業が従業員に対して、「退職」を「勧奨」するものです。
企業側としては、「退職してほしい」という動機・目的をもって実施してるため、その目的を達成するために、強引な説得をしてしまいがちです。
退職勧奨はあくまでも「勧奨」するだけであり、勧奨に応じるかどうか意思決定を行うのは従業員本人であるため、退職勧奨そのものに対する法律上の規制はありません。
もっとも、過度な勧奨行為により、従業員の自由な意思決定を阻害する事情がある場合には、従業員による退職の意思表示が取消し・無効となってしまう場合がありますので、注意が必要です。
この点について、東京地裁平成23年12月28日判決は、「労働者が自発的な退職意思を形成するために社会通念上相当と認められる程度を超えて、当該労働者に対して不当な心理的威迫を加えたりその名誉感情を不当に害する言辞を用いたりする退職勧奨は不法行為となる」と判断しており、裁判においては一定の判断基準となっています。
□従業員が退職を拒否しても退職勧奨を継続してよいか?
裁判例で問題となるケースの一つとして、従業員が退職を拒否する意思を明確にしているにもかかわらず、企業側が執拗に退職勧奨を行うというケースがあります。
従業員が一貫して退職勧奨に応じない旨を表明しているにもかかわらず、約2カ月の間に11回、1回につき約20分~約2時間の退職勧奨を行ったという事案で、退職勧奨が違法とされ慰謝料が認められた裁判例があります。
□誤った事情を伝えて退職勧奨を行ってもよいか?
よくあるケースが、「退職に応じないのであれば解雇になる」と伝えて退職に応じされようとするものです。
客観的にみれば解雇するほどの合理的理由・社会的相当性がないにもかかわらず、解雇が相当であるかのように伝えて退職に応じた場合に、退職の意思表示が錯誤により無効と判断した裁判例もありますので注意が必要です。
事実上も法律上も誤ったことを伝えて退職勧奨を行う場合には、退職の意思表示が無効とされてしまう場合があることに注意が必要です。
企業側として退職に応じないのであれば解雇を検討せざるを得ないような場合には、「なぜ解雇を検討せざるを得ないのか」という理由(解雇理由に該当する具体的事実)を具体的な根拠をもとに丁寧に説明した上で、従業員の理解を求めるように努めるべきでしょう。
□退職合意が成立した場合には書面の作成を

従業員が退職勧奨に応じてくれたと思っていても書面に残していない場合に、後で退職の合意の成立を争われることがあります(「辞めますなんて言ってない」、「無理やり言わされたので事実上は解雇だ」)。
このような紛争を防ぐために辞表を提出してもらうか、退職合意書を作成するかのいずれかをすることが必要でしょう。
このような書面を作成する場合には、退職勧奨を行ったその場で署名押印を求めると後で「無理やり署名押印をさせられた」と主張されるリスクがありますので、いったん書面を持ち帰ってもらい後日署名押印したものを持参してもらうことが望ましいといえます。
□退職勧奨を実施する場合には焦らず丁寧な対応を
以上のとおり、退職勧奨は解雇に比して法的リスクが低いとはいえ、企業側にとって無制限に実施できるわけではありません。
退職勧奨を実施しなければならない場面では、焦りが生じてしまう場合もあるかと思いますが、正確な情報・知識を前提に焦らず、丁寧な対応を心がけることが必要となります。
◆関連するコラムはこちらです◆
■記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
■当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
■本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。
関連する記事はこちら
- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~
- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~




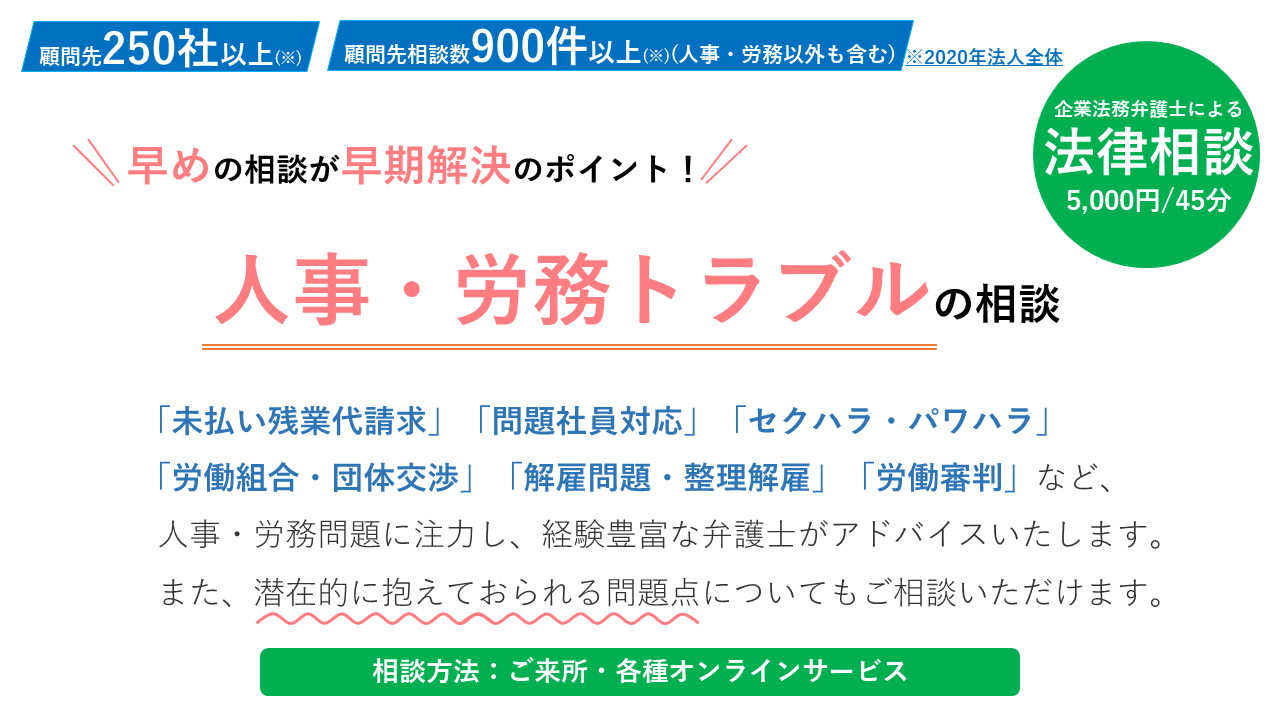
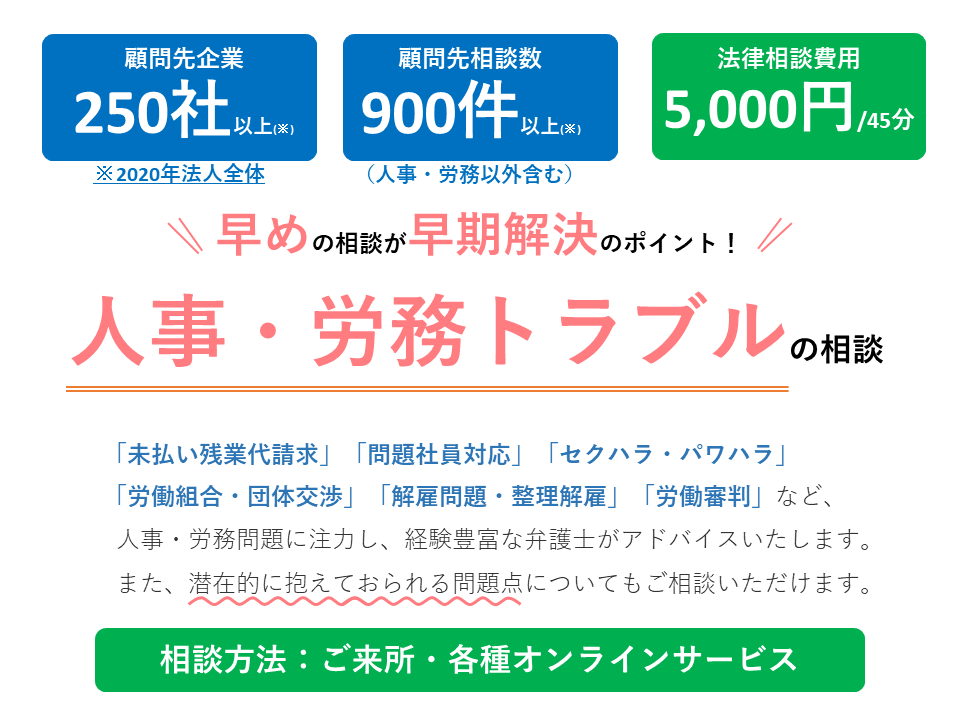
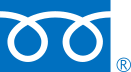 法律相談予約
法律相談予約










