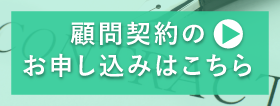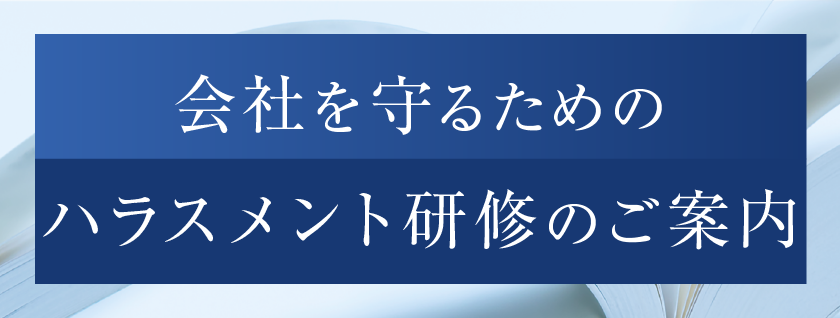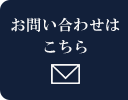2024.11.7
障害者雇用の職員に対する安全配慮義務違反が認められた事例~奈良地裁葛城支部令和4年7月15日判決(労働判例1305号47頁)~(弁護士 五十嵐 亮)
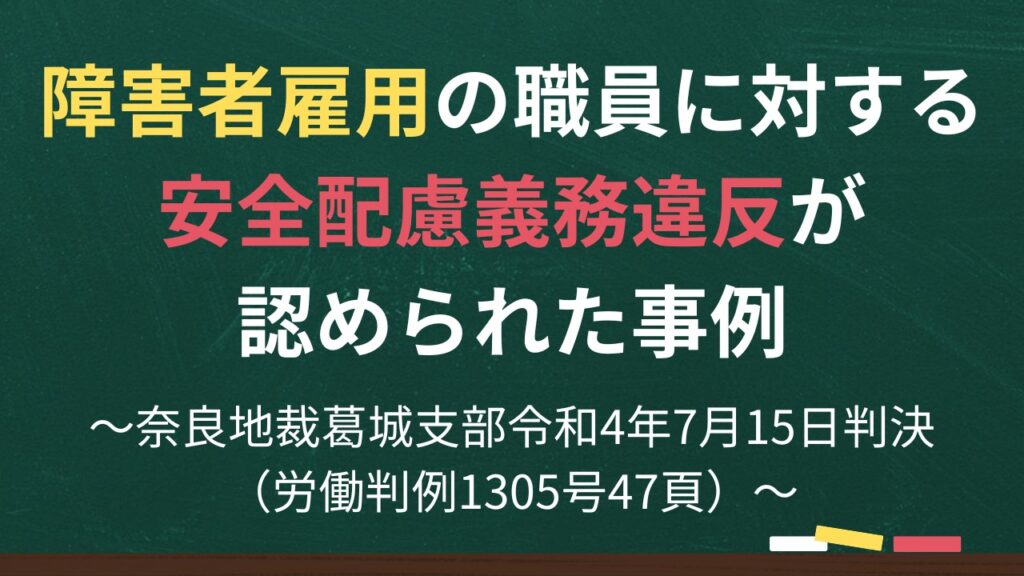
事案の概要
当事者
被告(Y市)は、地方自治体である。
原告(X)は、昭和61年4月1日に一般職員としてY市に採用されたものである。
原告の障害の状況
原告は、平成9年に交通事故に遭い、右足関節捻挫等のけがを負ったが、完治せず、右足関節機能障害により後遺障害が残り、平成10年に奈良県から右足関節機能障害5級の身体障害者手帳の交付を受けた。
Y 市では、平成16年から自己申告制度が開始され、Xは、自己申告書の「人事上の配慮が必要な病名等」及び「異動に際して特に配慮が必要なこと」の項目に「下肢肢体不自由5級」と記載した。
原告の人事異動の状況と症状

平成16年4月、Xは、年金事務(庁舎外での勤務が少ない)を担当するA課に配属されたが、平成17年4月から、生活保護を担当するB課にケースワーカーとして配属され、生活保護受給者の自宅を訪問する業務に多くの時間を費やすようになった。
Xの生活保護受給者の自宅の訪問回数は、平成19年、平成20年ともに400回を上回っていた。
訴訟の内容
Xは、Y市に対し、Xの身体障害を把握しているにもかかわらず、外勤業務を行う部署に配置し続けた等の安全配慮義務違反により、最終的に足関節固定術を受けるまでの状態に至った等の慰謝料として合計1100万円の支払いを求めて
提訴した。
本件の争点
本件の主な争点は、Y市に安全配慮義務違反があったか否かという点である。
裁判所の判断
安全配慮義務違反について
裁判所は、「労働者が現に健康を害し、そのため当該業務にそのまま従事するときには、健康を保持する上で問題があり、あるいは健康を悪化させるおそれがあるときには、速やかに労働者を当該業務から離脱させ、又は他の業務に配転させるなどの措置を取るべき義務を負うと解するべきである」と判断した。
本件について
裁判所は、B課に配属させた後のXの右足は、自宅訪問の業務が大きな負担となるような状態にあり、Y市もその事実について、自己申告書や身体障害者手帳のコピーで把握するとともに、同僚等を通じて実情を容易に知り得る状態に
あったと認められることから、Y 市としては、Xの状況を把握した上で、その業務負担を軽減する措置を取り、あるいは担当業務を変更するなどの措置を負っていたというべきであると判断した。
にもかかわらず、平成17年以降、XをB課から異動させず、多数回の自宅訪問に従事させたのであるから、Y市には安全配慮義務違反があるというべきであると判断した。
結論
裁判所は、Y 市の安全配慮義務違反を認め、Xに対して合計330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)の支払いを命じたものである。
本件のポイント
本件では、結論として使用者であるY市の安全配慮義務違反が認められました。
裁判所は、「Y市もその事実について、自己申告書や身体障害者手帳のコピーで把握するとともに、同僚等を通じて実情を容易に知り得る状態にあったと認められる」と認定し、Y 市がXの症状について把握していたことを重視して
いるため、使用者が労働者の障害について把握した場合には、障害に負担がかかるような業務に従事させることは避けるべきでしょう。
また、裁判所は、XをB 課から異動させず、多数回の自宅訪問に従事させたことをもって安全配慮義務違反としています。
本件のような地方自治体であれば、異動させられる他の軽易な業務があると思われます。
もっとも、小規模事業者で異動可能な業務が限られている場合に、同様なケースが発生した場合、労働者に対してどのような措置を取るかについては慎重に対応する必要があります。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2024年9月5日号(vol.296)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- タイムカード等で労働時間管理をしていない場合に概括的な認定が肯定された事例~福岡地裁令和5年6月21日判決(労働判例1332号86頁)~
- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~


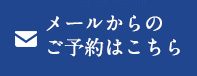

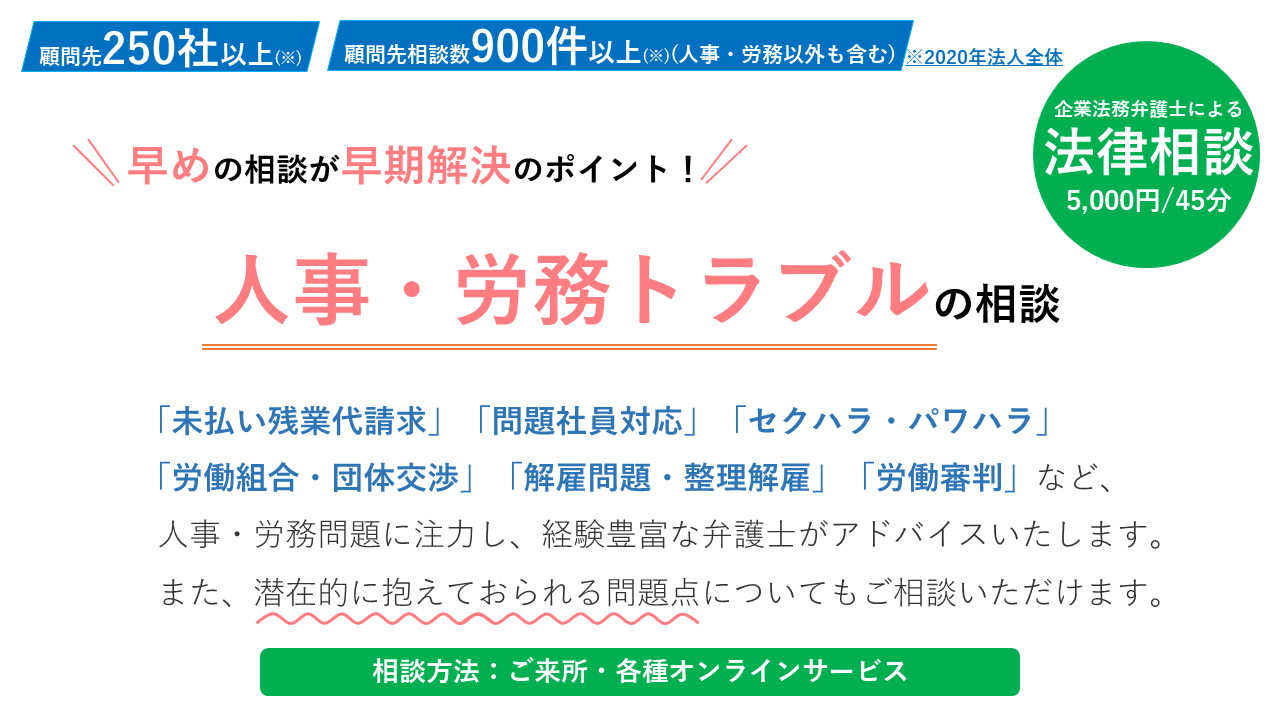
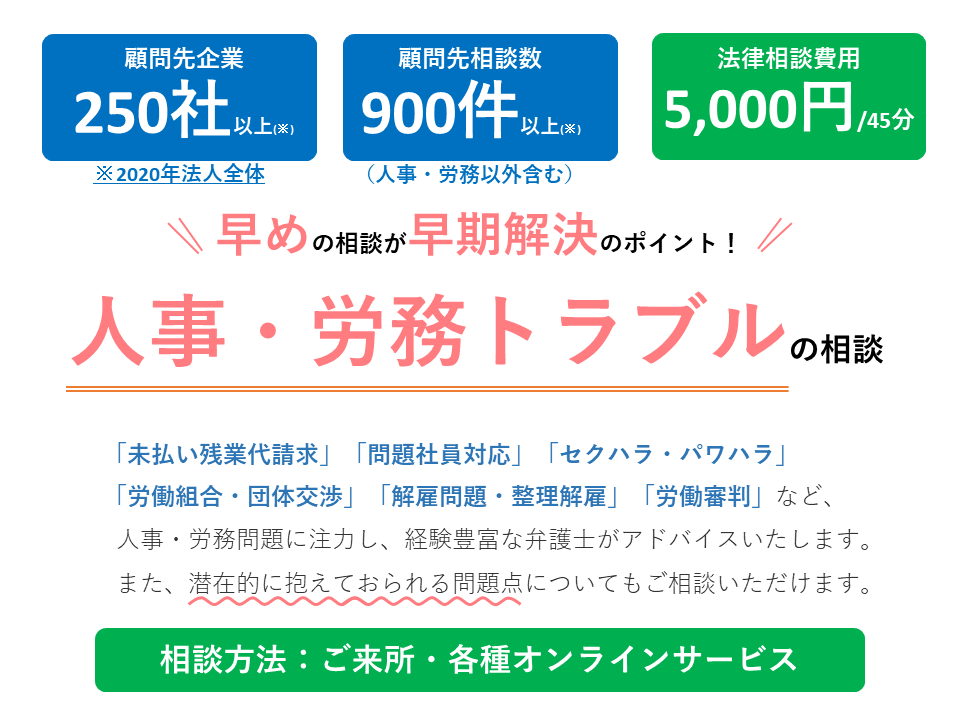
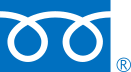 法律相談予約
法律相談予約