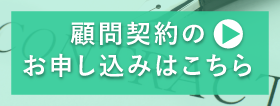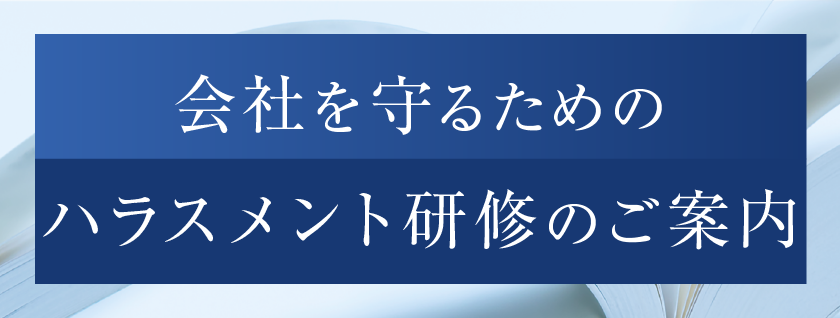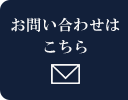2020.10.20
育休復帰後の正社員を契約社員に変更することが適法とされた事例 ~東京高裁令和元年11月28日判決~(弁護士:五十嵐亮)

事案の概要
当事者
原告であるXは、Y社が運営する語学スクールの講師をしていた者である。
被告であるY社は、語学スクールの運営等を目的とする株式会社である。
正社員から契約社員に変更された経緯
Xは、長女を出産したことから、1年間の育児休業を取得したが、長女の保育園が決まらないため、育児休業を6か月間延長したが、その後も保育園が決まらなかった。
Xは、Y社に対し、「夫には頼りたくない」、「無認可保育園は信用できず、ベビーシッターも夫が家に人が入るのを嫌がるので検討しない」と伝え、さらに3か月間の休職を求めたが、Y社は、Xはすでに最長期間の育児休業を取得しており、休職の要件に該当せず、特例は認められないとして、休職を認めなかった。
具体的な時系列は以下の表のとおりである。
| 平成25年3月 | Xが長女を出産 平成26年3月まで産休・育休を取得 |
| 平成26年2月 | Y社がXに対し、育休復帰後の勤務形態として1日の所定労働時間を短縮した正社員(時短勤務)及び週3日勤務の契約社員があることを説明 |
| 保育園が決まらないため、育休を6か月延長 | |
| 平成26年7月 | その後も保育園が決まらず、3か月の育休延長を求めたが、Y社は育休延長を認めず |
| 平成26年9月 | Xが、Y社が提示した週3日勤務の契約社員(契約期間1年)となる内容の雇用契約書に署名(本件合意) |
| 保育園が見つかったとして正社員に戻すように求めたが、Y社はこれに応じず | |
| 平成27年7月 | 7月末日をもって1年の契約期間満了により雇止め(本件雇止め) |
Xの請求内容
Xは、Y社に対し、本件合意は、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)9条3項及び育児介護休業法(以下「育介法」)10条に違反し無効であることを理由に、正社員の契約はなお存続すると主張し、正社員としての地位の確認及び雇止め後の平成26年8月分以降の未払い賃金の支払いを求めたものである。
本件の争点
本件では、主に、①本件合意が均等法9条3項及び育介法10条に反し無効となるかどうかという点及び②本件雇止めが適法かという点が争点となった。
裁判所の判断
争点①について
裁判所は、本件合意は、Y社における正社員と契約社員の労働条件を単純に比較すると、正社員の給与が月額48万円(固定残業代含む)であるのに対し、契約社員が10万6,000円であり、正社員は雇用期間が定められていないのに対し、契約社員は、契約期間が1年であることからすれば、不利益があることは否定できないとしつつも、結論としては、本件合意は、均等法9条3項及び育介法10条が禁止する「不利益な取扱い」には当たらないと判断した。
その上で、判断の理由として、
- Xは、保育園が見つからず、家族のサポートも受けられないため、正社員のままであれば、仮に時間短縮措置を講じたとしてもクラスを担当することが困難になったり、欠勤を繰り返すなどして解雇されるおそれがある状況にあった
- Y社は、育休明けの従業員に対し多様な雇用形態を設定し、「正社員(週5日勤務)」、「正社員(週5日の時短勤務)」の他「契約社員(週3日勤務)」の中から選択することができるように就業規則の見直しを行い、契約社員制度を導入し、Xにも説明していた
- Xには、復職までの6か月の間、復職する際の自己に適合する雇用形態を十分に検討する機会が与えられていた
- 育介法等が定める最長の育児休業を取得した労働者に対し、さらに長期の休職を認めることが事業者に義務付けられているものではない
等の事情を指摘した。
争点②について
裁判所は、結論として、本件雇止めは、客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当であり、適法であると判断した。
判断の理由として、以下のような事情が挙げられている。
- Xは、平成26年9月に育児休業から復帰した直後から、無断で執務室内の会話を録音していたところ、Y社が録音を止めるよう求めても録音を止めなかった
- Xは、執務室内における録音をしない旨を約する確認書を自ら提出したにもかかわらず、これを破棄して録音した
- Xは、マスコミに対し、録音した音声データを渡した
- Xは、マスコミに対し、保育園に決まった事実がないのに「保育園が決まったのに正社員に戻すことを渋った」と話した
本件のポイント
本件は、育児休業の期間中に保育園が決まらず、時間短縮の措置を講じても正社員としての業務に支障がある事案において、契約社員に変更することについて、違法ではないという判断を裁判所が示したものであり、均等法9条3項及び育介法10条における「不利益な取扱い」に該当するか否かの判断をする際に参考になる裁判例です。
契約社員に変更後、雇止めを行ったことについては、一審の東京地裁は違法としているのに対し、高裁が適法とし判断が異なっていることから、慎重な対応が必要といえるでしょう。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2020年8月5日号(vol.247)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- タイムカード等で労働時間管理をしていない場合に概括的な認定が肯定された事例~福岡地裁令和5年6月21日判決(労働判例1332号86頁)~
- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~


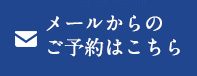
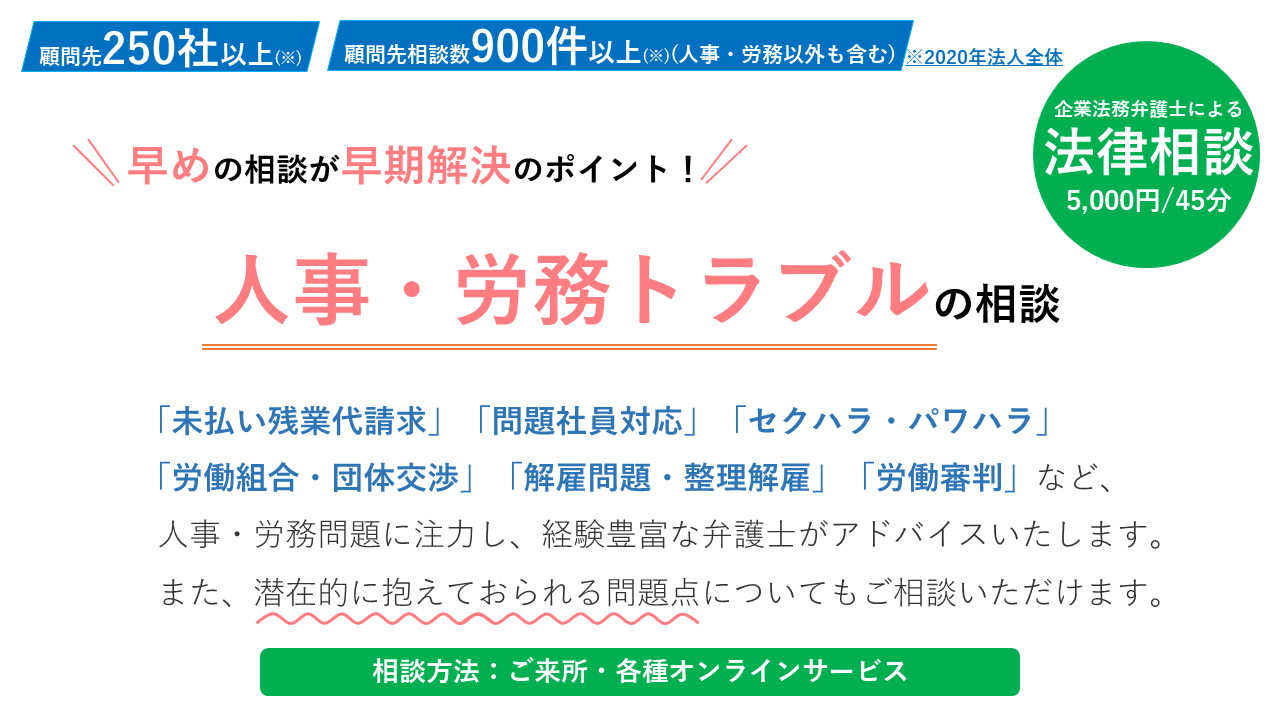
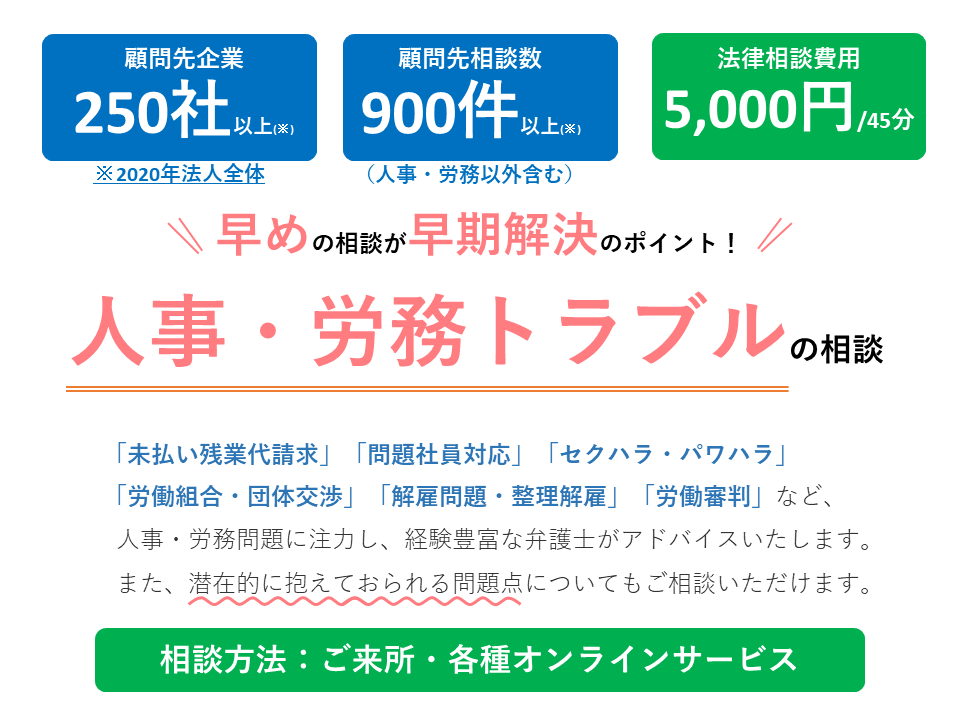
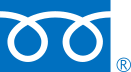 法律相談予約
法律相談予約