2025.11.7
商品形状の模倣!?
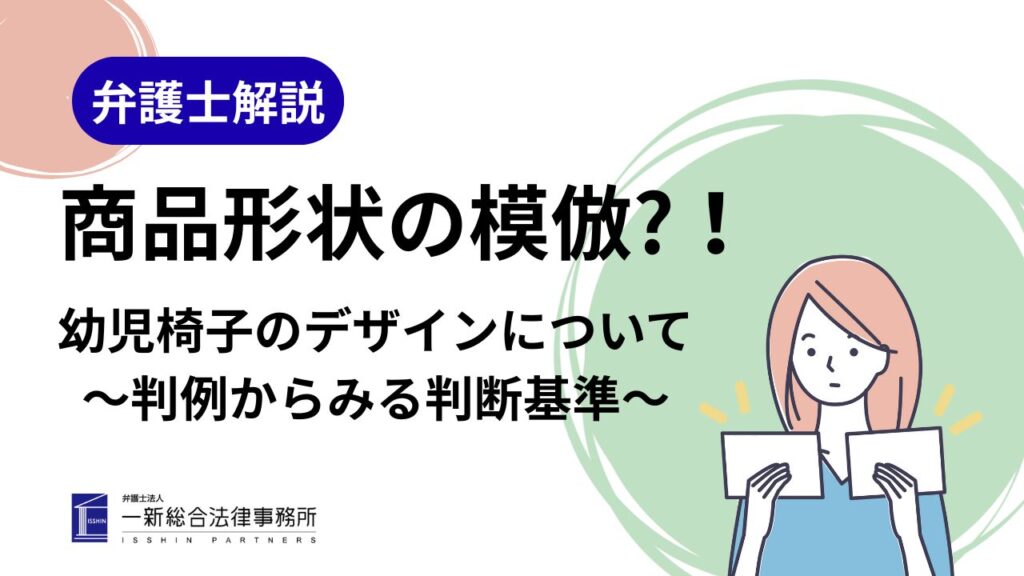
事案の概要
幼児用の椅子で人気のストッケ社「TRIPP TRAPP」について、独占的利用権を有するストッケ社と、著作権を有するオプスヴィック社が、共同原告となって類似形態の椅子を販売していた被告会社に、次の①~③のいずれかに当たるとして、製品の製造販売の差止・廃棄、及び損害賠償、謝罪広告を求めた事案です。

原告らの主張根拠
①原告らの商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為(不競法2条1項1号、2号)に該当する。
②仮に①に該当しないとしても、原告製品について、原告オプスヴィック社が有する著作権及び原告ストッケ社が有するその独占的利用権の各侵害行為(著作権法21条、27条)に該当する。
③仮に①②に該当しないとしても、取引における自由競争の範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害する不法行為(民法709条)。
不正競争防止法違反の主張
特に、上記①不正競争防止法違反の争点において原告は、主位的には、製品全体の形態が商品等表示に該当すると主張し、予備的には、本件製品の次の2つの特徴からなる形態的特徴が商品等表示に該当する
【特徴1】
左右一対の側木の2本脚であり、かつ、座面板及び足置板が左右一対の側木の間に床面と並行に固定されている点
【特徴2】
左右方向から見て、側木が床面から斜めに立ち上がっており、側木の下端が、脚木の前方先端の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、側木と脚木が約66度の鋭角による略L字型の形状を形成している点
旨主張しました。
裁判所の判断
不正競争防止法違反について
裁判所は、不正競争防止法の規定の趣旨は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等し、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認、混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより、周知性ある商品等表示の有する出所表示機能を保護し、事業者間の公正な競争を確保する点にあるとした上で、「商品の形態そのものであっても、客観的に他の同種商品とは異なる特別顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、その形態が、特定の事業者によって長期間、継続的独占的に使用されることにより、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、その形態を有する商品が当該特定の事業者の出所を表示するものとして需要者に周知になっていれば(周知性)、出所表示機能を備えるに至ることもある」と判示し、その上で、本件製品は左記特徴1及び2に加えて
【特徴3】
側木の内側に形成された溝に沿って座面板と足置板の両方をはめ込み固定する点
まで揃って初めて特別顕著性が認められるのであり、特徴1と2だけでは特別顕著性は認められない。
被告商品は特徴3は満たしてないので類似とは認められないと判断しました。
著作権法違反について
実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合又は当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合に限られると解するのが相当であるとした上で、本件顕著な特徴(特徴1~3)を備えた原告製品は、椅子の創作的表現として美感を起こさせるものではあっても、椅子としての実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象とすることができるような部分を有するということはできないし、被告製品は特徴3を備えていないとして、著作権法違反にも当たらないと判断しました。
ポイント
本判決は次の2点において、今後の参考となる判断が示されています。
1点目は、不正競争防止法の商品の形態そのものに出所表示機能が認められる場合の要件について「特別顕著性」と「周知性」の2要件が必要である旨を示した点です。
2点目は、応用美術に関して著作物性が認められる場合について、一般の著作物より高度の基準となる事を示した点です。判例では、一般の著作物と同様の基準で判断すると、著作権は、意匠法と違い、審査登録の手続きを経ずに創作と同時に権利が認められることから、権利関係が複雑になって混乱が生じることとなり、また著作権の保護期間が長期であることも相まって「公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する」という著作権法の目的から外れることになるおそれがあることを指摘し、実用品については、その機能を実現するための形状等の表現につき様々な創作・工夫をする余地があるとしても、著作権法により保護しなくても、意匠法によって保護することが可能であると説明されています。
従前の裁判例でも、応用美術については、一般著作物より高度の基準が課される傾向がありましたが、本判決では、理由等を示した上で、高度の基準を課すべきとの判断が示されました。
商品のどこに特徴があり、どこまで保護すべきか、文化の発展との間で非常に悩ましいところです。
みなさんは、二つの製品を見比べて、この判決の結果についてどのように感じられたでしょうか。
商品購入にあたって、製品の創作的表現に対してどのような姿勢で臨むかは、一消費者の個々の判断に委ねられているといえます。
商品購入時の選択こそ、創作的表現に対するリスペクトを示す一番の解決策だろうと思います。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年9月5日号(vol.307)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。




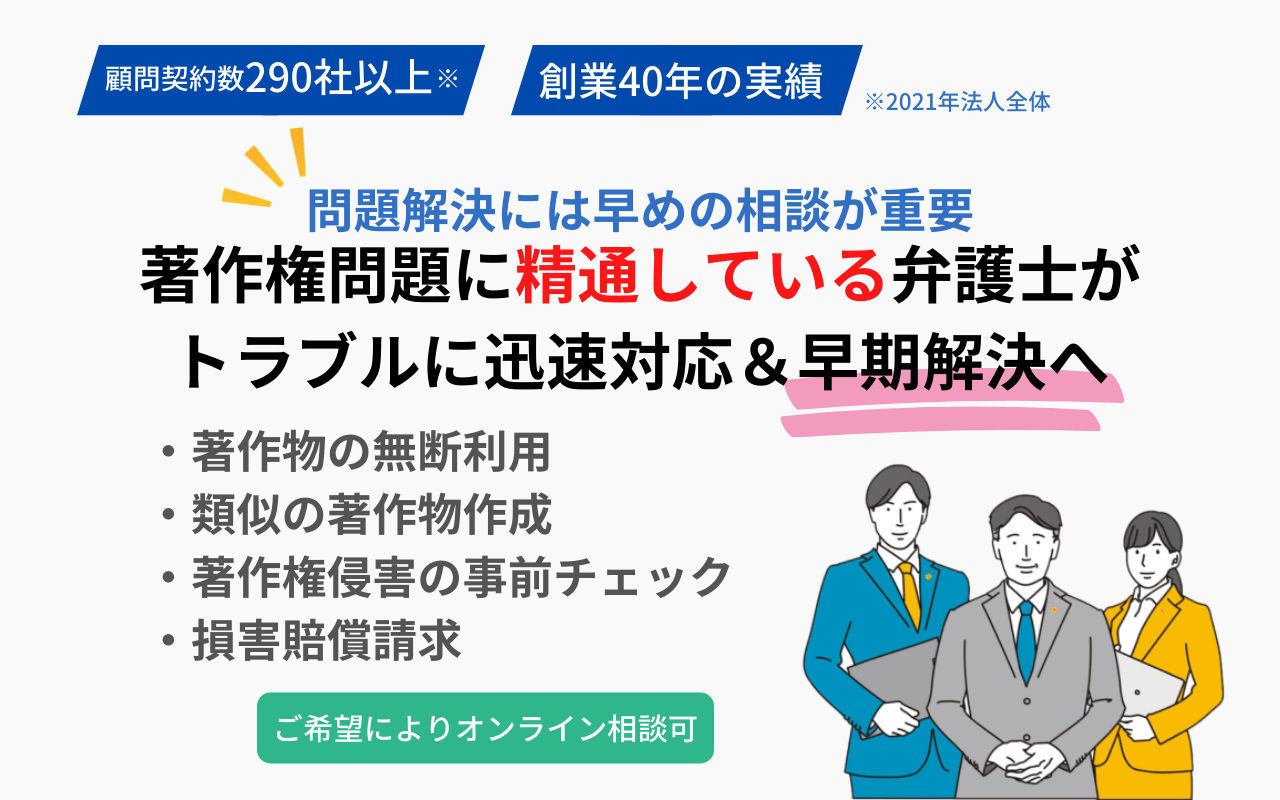
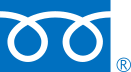 法律相談予約
法律相談予約










