2025.10.8
求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
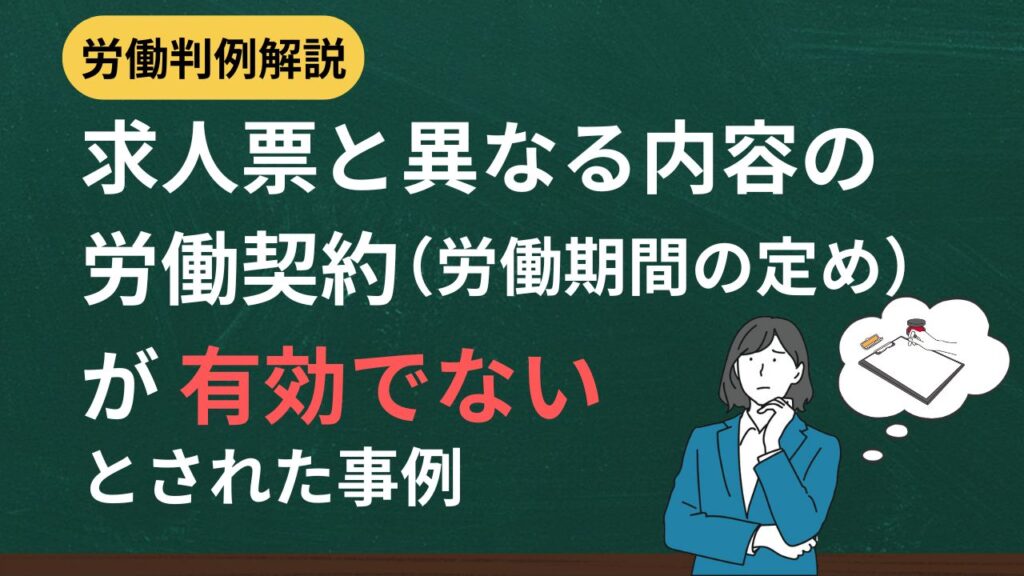
事案の概要
当事者
被告(Y社)は、人材派遣業を主な目的とする株式会社である。
原告(X)は、令和5年7月3日からY社において勤務を開始した者である。
採用内定・契約満了に至る経緯
令和5年6月19日、Xは、求人票を見て、Y社によるウェブ面接を受け、同日、Y社は、Xに対し、同年7月1日を勤務開始日として採用内定通知をした(本件内定通知)。
同年6月21日、XとY社は、Y社事務所において労働契約書を作成した(本件労働契約)。
Xは、同年7月3日から、Y社にて勤務を開始したが、Y社は、令和5年8月31日に契約期間が満了したとして、Xの就労を拒否している。
求人票の記載内容
Y社の求人票には、概要、以下のような記載があった。
| ア 雇用形態 | 正社員 |
| イ 雇用期間 | 定めなし |
| ウ 試用期間 | あり 期間2カ月 |
| エ 職種 | 人材コーディネーター (栗東営業所) |
| オ 仕事内容 | 人材派遣会社にて営業職 |
| カ 就業場所 | 栗東営業所 |
| キ 賃金 | 基本給 月額25万円 固定残業代 なし |
労働契約書の記載内容
他方、労働契約書には、概要、以下のような記載があった。
| ア 雇用期間 | 令和5年7月1日~令和5年9月30日 ※雇用期間の末日について、9月30日から8月31日と捨印訂正されている。 |
| イ 賃金 | 基本給 月額25万円 諸手当 通勤手当その他手当は所内規程による 賃金締切日 毎月末日 |
Xによる請求内容
Xは、Y社に対し、期間の定めのない労働契約が成立し、現在も継続していると主張し、労働者としての地位確認及び未払賃金の支払いを求めて提訴した。
本件の争点
本件の争点は、XとY社との労働契約は、令和5年8月31日をもって期間満了によって終了したかという点である。
裁判所の判断
裁判所の判断の骨子
裁判所は、本件内定通知により、就労開始を令和5年7月1日とする始期付労働契約が成立したと解した上で、本件労働契約は、始期付労働契約を変更する合意に当たると解釈し、かかる変更の合意が有効かどうかについて検討・判断した。
始期付労働契約の成立の点について
裁判所は、Y社の求人票では、配置先、仕事内容、賃金といった労働契約のおおむねの要素が具体的に特定されており、本件内定通知の際に原告に勤務開始日が伝えられていることから、本件内定通知は、Xの求人応募(=労働契約の申込み)に対する承諾の意思表示とみることができることから、本件内定通知により、就労開始を令和5年7月1日とする始期付労働契約が成立したと判断した。
変更合意(本件労働契約)の有効性について
その上で、裁判所は、本件労働契約について、始期付労働契約のうち雇用期間等についての労働条件を変更する合意であると解し、かかる変更合意が有効か否かについて検討した。
この点について、裁判所は、雇用期間を期間の定めのないものから、2か月という短期の雇用契約に変更するという合意が有効となるためには、当該合意が、労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要であると判断した。
本件では、契約期間に関し相当の不利益変更であるにもかかわらず、変更の際にどのような説明がなされたか明らかでないこと等を理由として、変更の合意は有効ではないと判断した。
結論
裁判所は、雇用期間を期間の定めのないものから、2か月という短期の雇用契約に変更するという合意が有効ではないとして、本件労働契約は終了していないとして、Xによる地位確認及び賃金請求を認めた。
本件のポイント
本件は、求人票には「期限の定めなし」と記載されていたにもかかわらず、労働契約書には雇用期間が2か月とされていたことから、トラブルになった事案です。
本件では、外形上は、本件内定通知をした後に本件労働契約が締結されたものですが、本件内定通知によって始期付労働契約が締結され、本件労働契約によって期間の定めが変更されたと解釈された点が特徴的です。
また、期間の定めなしから雇用期間2か月に変更することは不利益が大きいことを重視され、変更の合意が有効となるための要件が厳しく判断されました。
求人票の記載の労働条件を労働契約の段階になって変更する場合には、丁寧な説明が必要となりますので、注意が必要です。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年8月5日号(vol.306)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~
- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~
- 海外渡航目的の年次有給休暇に対する時季変更権の行使を適法とした事例~札幌地裁令和5年12月22日判決(労働判例1311号26頁)~




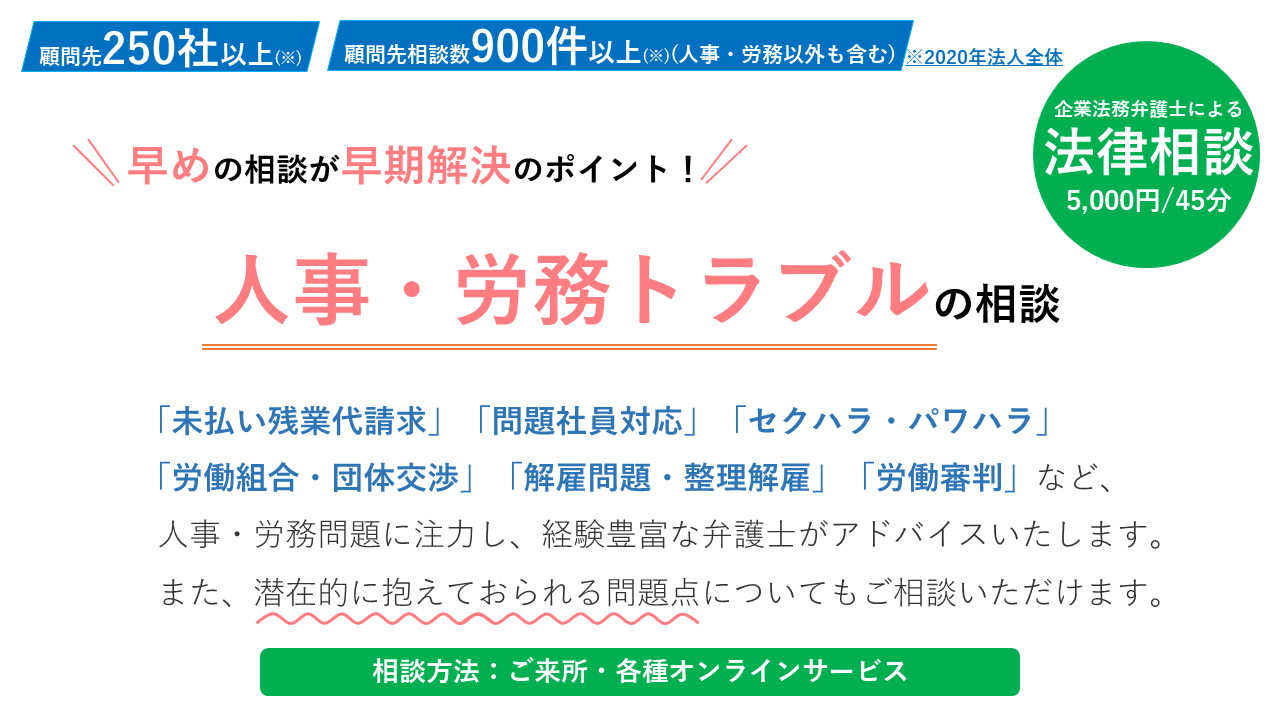
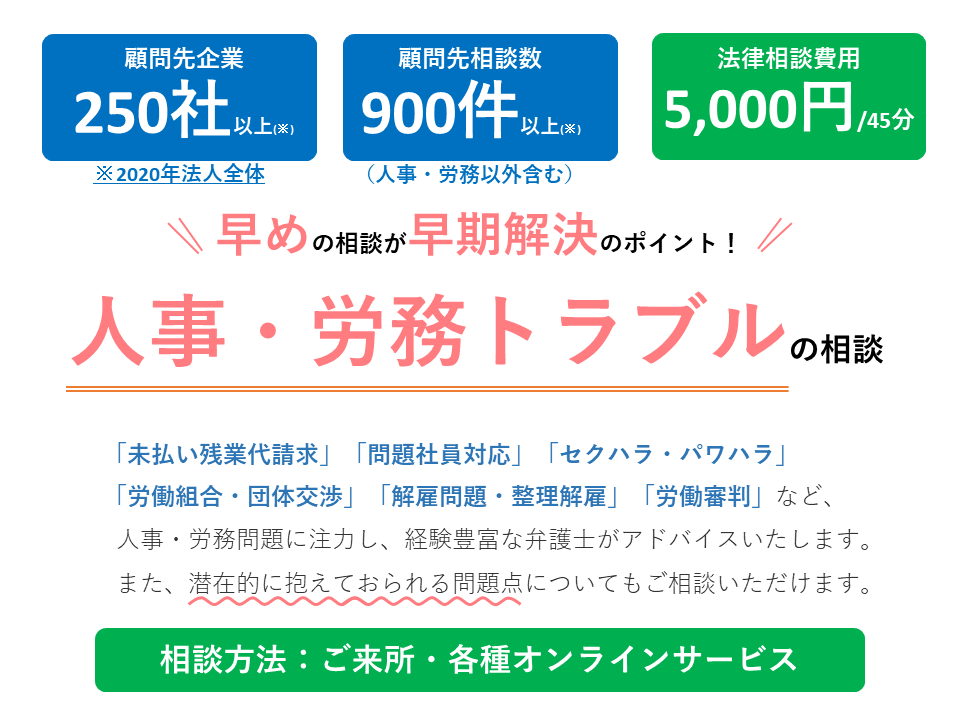
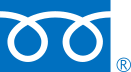 法律相談予約
法律相談予約










