2025.11.27
公正証書がデジタル化!(弁護士 今井 慶貴)
※この記事は、株式会社東京商工リサーチ発行の情報誌「TSR情報」で、当事務所の理事長・企業法務チームの責任者 弁護士今井慶貴が2017年4月より月に一度連載しているコラム「弁護士今井慶貴のズバッと法談」を引用したものです。
第103回のテーマ
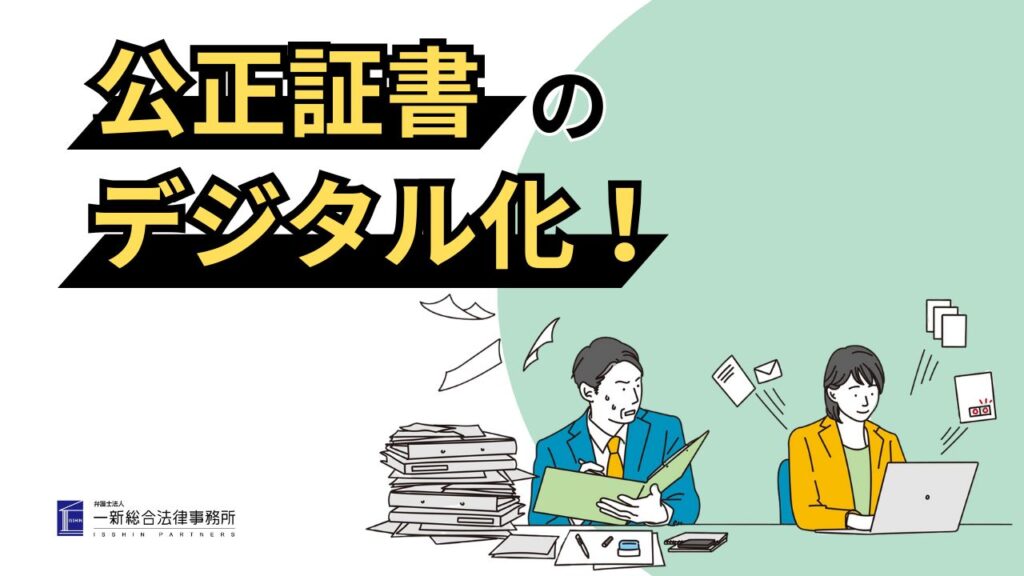
この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムです。
気楽に楽しんでいただければ幸いです。
今回のテーマは、「公正証書がデジタル化!」です。
その1.公正証書のデジタル化がスタート
本年10月から改正公証人法が施行され、公正証書に関する一連の手続のデジタル化がスタートしました。
デジタル化に対応する公証人(指定公証人)は施行日以降順次指定され、新潟県内の公証役場では12月にスタートとなります。
デジタル化により、まず嘱託(申請)の方法が変わります。
これまでは公証役場に出向き、印鑑証明書などを提出して本人確認を受ける必要がありましたが、今後は出頭せずにオンラインで嘱託ができ、マイナンバーカードなどを用いた電子署名による本人確認も可能となります。
また、公証人による陳述聴取や内容確認も、嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議の利用が可能になります。
ただし、リモート参加をするためには、画面共有が可能なパソコン、ウェブカメラ、マイク、スピーカー、タッチ入力可能なディスプレイ(またはペンタブレット)、メールアドレスなどが必要です。
さらに、公正証書の作成・保存方法も大きく変わります。
これまでは公証人と嘱託人が署名押印して紙の原本を作成して、それを保存していましたが、今後は原則として電子データとして作成・保存されます。
嘱託人は公正証書の内容を確認して電子サインをして、公証人が官職証明書を用いて電子署名を行います。
押印は不要となります。
その2.作成された公正証書の閲覧等は?
作成された公正証書は、これまでは公正証書の正本・謄抄本を書面で交付されていましたが、今後は、電子データとして閲覧や交付を受けることができるようになりました。
閲覧は、画面上で表示する方法のほか、電子データを紙に出力して確認することもできます。
正本や謄本も、従来どおり紙で交付を受けることができるほか、電子データとしてメールやクラウド経由で受け取ることも可能です。
また、USBメモリなどの記録媒体で提供を受けることも認められます。
このデジタル化に併せて、公証人手数料令の見直しによって、手数料の適正化が図られました。
なお、ある公証人の方からは、デジタル化に伴う公正証書作成のシステムがこなれておらず、従来よりも作成に時間がかかって大変だという声を聞きました。
慣れもあるのかもしれませんが、システムの問題であれば、改善が期待されます。
最後に一言。
最後に一言。
現在、来年5月施行の民事訴訟のデジタル化フェーズ3(訴状などの申立てのオンライン化、訴訟記録の電子化)に向けて、裁判所も弁護士会も準備に向けて余念がありませんが、民事司法システムの一翼を担う公証人役場もひっそりと(?)デジタル化が進んでいたのでした。
~デジタル化が真の利便性につながるように!~
一新総合法律事務所では、「契約書のリーガルチェック」「取引先とのトラブル」「事業承継」「消費者クレーム対応」「債権回収」「コンプライアンス」「労務問題」など、企業のお悩みに対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。















