2025.10.29
住宅セーフティネット制度の見直し(弁護士 今井 慶貴)
※この記事は、株式会社東京商工リサーチ発行の情報誌「TSR情報」で、当事務所の理事長・企業法務チームの責任者 弁護士今井慶貴が2017年4月より月に一度連載しているコラム「弁護士今井慶貴のズバッと法談」を引用したものです。
第102回のテーマ
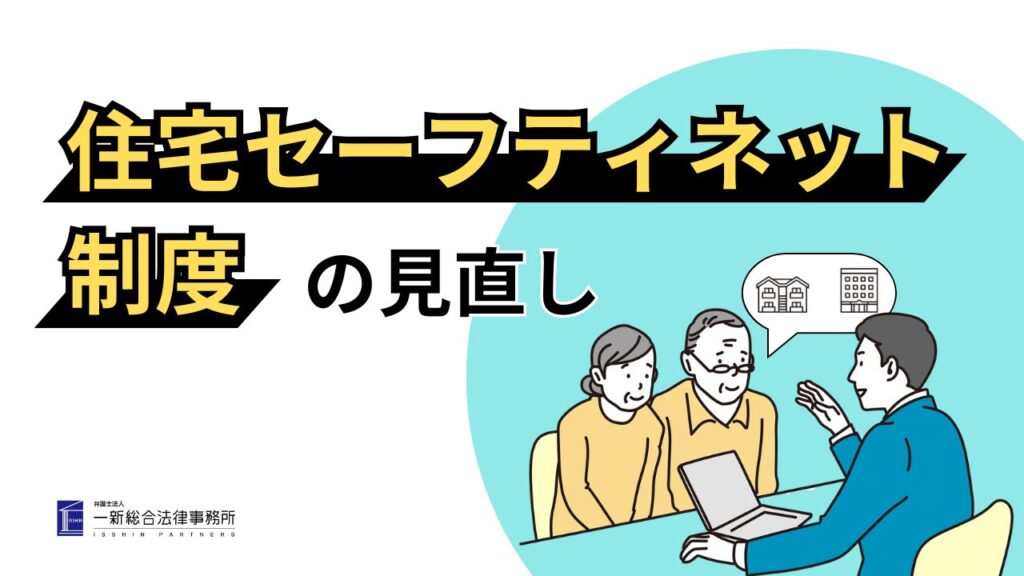
この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムです。
気楽に楽しんでいただければ幸いです。
今回のテーマは、「住宅セーフティネット制度の見直し」です。
その1.住宅セーフティネット法の改正
この10月から、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)の改正法が施行されました。
単身世帯の増加、持家率の低下等により、要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが高まることが想定されています。
しかし、孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後の課題への不安から、単身高齢者など要配慮者に対する大家の拒否感が大きいことが課題となっていました。
そこで、大家と要配慮者のいずれもが安心して利用できる市場環境の整備などを目指して、今回の法改正がなされました。ポイントは4つです。
第1に、“賃貸借契約が相続されない”仕組みとして、“終身建物賃貸借”(賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する賃貸借)について、住宅ごとの認可から事業者の認可へと手続が簡素化されました。
第2に、“残置物処理に困らない”仕組みとして、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく死亡時の残置物処理を追加しました。
その2.法改正のポイント(続き)
第3に、家賃債務保証業者の認定制度の創設です。要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)を国土交通大臣が認定する仕組みができました。
(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者への保証リスクの低減も図られます。
第4に、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度の創設です。
市区町村長(福祉事務所設置)等が認定し、居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅の供給を促進します。
生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付を原則とすることや、入居する要配慮者は認定保証業者が家賃債務保証を原則引受けるものとすることで賃料支払いの不安が軽減します。
その他、市区町村による居住支援協議会設置を努力義務化し、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進することになりました。
最後に一言。
最後に一言。
私も不動産管理会社などから独居の高齢者等が亡くなられた後の対処についての相談を受けますが、実際問題として大家側の負担は相当なものがあります。
今回の法改正が、要配慮者への賃貸物件の供給にプラスに働くことを期待したいと思います。
~貸し手・借り手・支援者の三方よしに!~
一新総合法律事務所では、「契約書のリーガルチェック」「取引先とのトラブル」「事業承継」「消費者クレーム対応」「債権回収」「コンプライアンス」「労務問題」など、企業のお悩みに対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。















