2021.4.2
不祥事の根本原因は「空気」「風土」なのか?(弁護士:今井慶貴)
※この記事は、株式会社東京商工リサーチ発行の情報誌「TSR情報」で、当事務所の企業法務チームの責任者 弁護士今井慶貴が2017年4月より月に一度連載しているコラム「弁護士今井慶貴のズバッと法談」の引用したものです。
今月のテーマ(2021/3/29発行 TSR情報)
この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムです。
気楽に楽しんでいただければ幸いです。
今回のテーマは、不祥事の根本原因は「空気」「風土」なのか?です。
その1.不祥事の原因分析の終着点は?
近年、大企業等で世間を騒がす不祥事が起きると、「第三者委員会」などで徹底調査する→真の原因(真因)を究明する→再発防止策を提言する→それを世間に公表する、というのが一つのスタンダードになってきました。
経営者やアドバイザーにとっては、公表された報告内容は不祥事研究の宝庫ともいえます。
私も最近、研修会の講師をするために、最近の不祥事例についての公開資料をいくつか読む機会がありました。
不祥事の原因は、事案によってそれぞれですが、突き詰めていくと、組織において不祥事を「助長する」「容認(黙認)する」といった「空気」「風土」が存在する点で共通するようです。
それは他人事ではありません。
例えば、会社の中で次のようなことが行われる場合に「ノー」と言えるでしょうか?業界の競争環境が厳しい中で生き残りをかけて、顧客の利益にはならない商品
でも販売するノルマが課せられた。
納期にどうしても間に合わないので、製品の品質基準を少しだけごまかさざるを得ない。
会社で生きていくために、周りもやっているので……。
その2.原発のセキュリティも「忖度」が突破
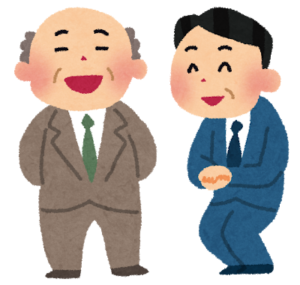
今年に入り、昨年9月に東京電力柏崎刈羽原発で中央制御室員が同僚のIDカードを使って中央制御室に不正に入域したという事案が報道されました。
この中央制御室員の人は、ロッカーの自分のIDカードが見当たらなかったため、非番である同僚のIDカードを無断で寸借し、同僚の名を名乗って入域を試みました。
警備員(委託業者と社員)は、違和感を覚えつつも、IDカードの識別情報を書き換えて入域を認めました。
翌日、同僚が自分のIDカードで入域しようとしたところ、エラーが出たため、本件は発覚しました。
東京電力の背後要因の分析の中には、「厳格な警備業務を行い難い風土」として、「社員に対する警備員の忖度」「警備業務に対する尊重の不足」「内部脅威に対する意識の不足」などが挙げられていました。
言語道断ではあるのですが、「ルールはあるけど、中央制御室員だから入っても(入らせても)、まあいいか」という意識だったんだろうなと、なんとなく分かってしまう自分もいます。
最後に一言。
「空気が読める」というのは美質である反面、「空気に抗えない」という欠点でもあります。
それがマイナスをもたらす現実をみると、そろそろ変えていかなくてはと思います。
いうなれば、長年にわたるサッカーの日本代表への評価みたいな話なのですが…
日本人には「個の力」がもっと必要だ。
■記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
■当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
■本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。















