2021.3.12
固定残業代の定めが無効とされた事例 ~宇都宮地裁令和 2 年 2 月19日判決~(弁護士:五十嵐亮)
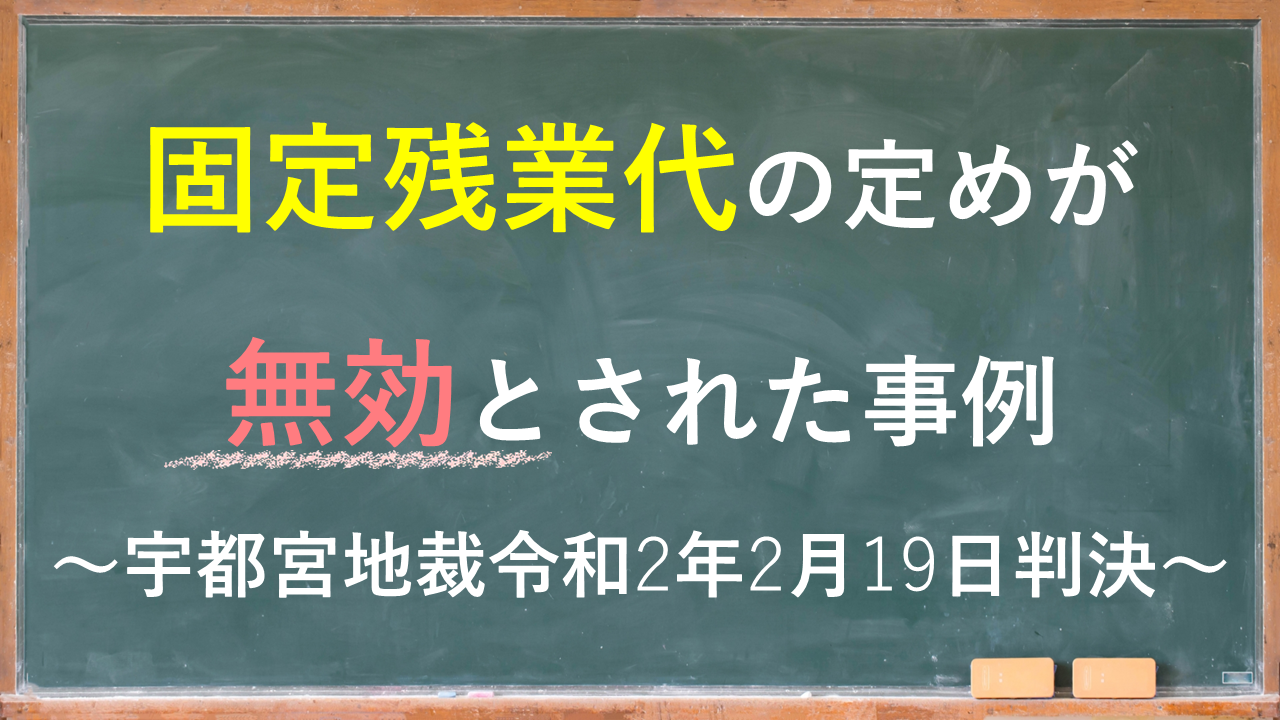
1. 事案の概要
(1)当事者
被告であるY社は、木造注文住宅の建築請負・販売等を行う株式会社である。
原告であるXは、建設関連上場企業に勤務経験があることから、幹部社員候補として紹介され、平成25年よりY社にて社長室長として勤務していた者である。
⑵ 本件における固定残業代の定め
ア 雇用契約書の記載(賃金部分のみ抜粋)
賃金 月額給与(日給月給制)
(a) 基本給 (能力給) 30万円
(b) 職務手当(定額残業手当) 28万3333円
イ 「給与に関する通知書」の記載
A 給与 月額58万3333円
その内訳・基本給(能力給) 30万円
職務手当 28万3333円
B 割増賃金を計算する基礎となる時間単価
1727円(30万÷173.75時間)
C 割増賃金の1時間当たりの単価 時間外労働
2159円(1727円×1.25)
D 時間外労働に対する労働時間数
131時間14分
E 留意事項
職務手当28万3333円は、「時間外労働に対する割増賃金の定額払い」です。
その内訳は、時間外労働は131時間14分に相当するものです。
ただし、実際の時間外労働が上記の131時間14分に満たなくとも、その分の返還を要求することはありません。
⑶ Xの時間外労働の状況
Xは、入社以来、月平均時間外労働は80時間を超えていた。
具体的には、80時間を超えた月が22か月あり、そのうち100時間を超えた月が6か月あった。
⑷ Xの請求内容
Xは、まず、Y社では、雇用契約書及び給与に関する通知書には固定残業代の記載があるが、給与明細の記載からは支払われた賃金のうちどの部分が通常の賃金でどの部分が割増賃金部分であるか判別できないため、定額残業代の定めは無効であると主張した。
また、本件における固定残業代の定めは、1か月あたり131時間以上もの時間に相当するものであって、労基法32条及び36条の趣旨に反するものであって、公序良俗(民法90条)に反することから、無効であると主張した。
その上で、Xは、未払い残業代合計859万円を請求する訴訟を提起したものである。
⑸ 本件の争点
本件の争点は、固定残業代の有効性であるが、さらに以下の2点が争点となった。
①毎月の給与明細に具体的に何時間分の時間外手当に相当するか記載する必要があるか(争点①)
②131時間に相当する固定残業代の定めは、長時間労働を助長するものとして公序良俗に反し無効となるか(争点②)
2. 裁判所の判断

(1) 争点①について
裁判所は、固定残業代について、一般論として、「雇用契約に係る契約書等の記載のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断するのが相当である」と述べた。
その上で、本件では、前記1⑵ア、イのとおり、職務手当が割増賃金の定額払いであること及び時間外労働は131時間14分に相当するものであることを明示していると判断した。
⑵ 争点②について
裁判所は、長時間の時間外労働に相当する固定残業代を定めることについて、一般論として、「実際には、長時間労働を恒常的に行わせることを予定していたわけではないことを示す特段の事情」が認められない限り、当該職務手当を1か月131時間14分相当の時間外労働等に対する賃金とする本件の固定残業代の定めは公序良俗に反するものとして無効となると述べた。
本件では、実際に、前記1⑶のとおり、80時間越えの時間外労働が続いていること等を理由として、上記「特段の事情」は認められないとして、本件の固定残業代の定めは無効と判断した。
3. 本件のポイント
本件では、争点①について、結果的にはXの主張を退けています。
これまでの最高裁判決も本件判決も契約書等において定額残業代とそれ以外の賃金が明確に区分されていれば足りるとし、必ずしも毎月の給与明細に何時間分の時間外手当に相当するか記載する必要はないとしています。
ただ、この点は、裁判例で争点とされることが多いため、紛争回避の観点から、毎月の給与明細において説明することも一つの方法でしょう。
また、争点②の点については、これまで裁判例においても判断が分かれていたところです。
本件の特徴は、「実際には、長時間労働を恒常的に行わせることを予定していたわけではないことを示す特段の事情」の有無という基準を示したところにあり、長時間労働を前提とした固定残業代制度の下で、実際に長時間労働をさせている場合には、固定残業代が無効とされるリスクが大きくなるといえます。
ただ、この点については、何時間までなら有効なのか(45時間なのか、80時間なのか)必ずしも明らかになっていないため、注意が必要です。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2021年1月5日号(vol.252)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~
- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~




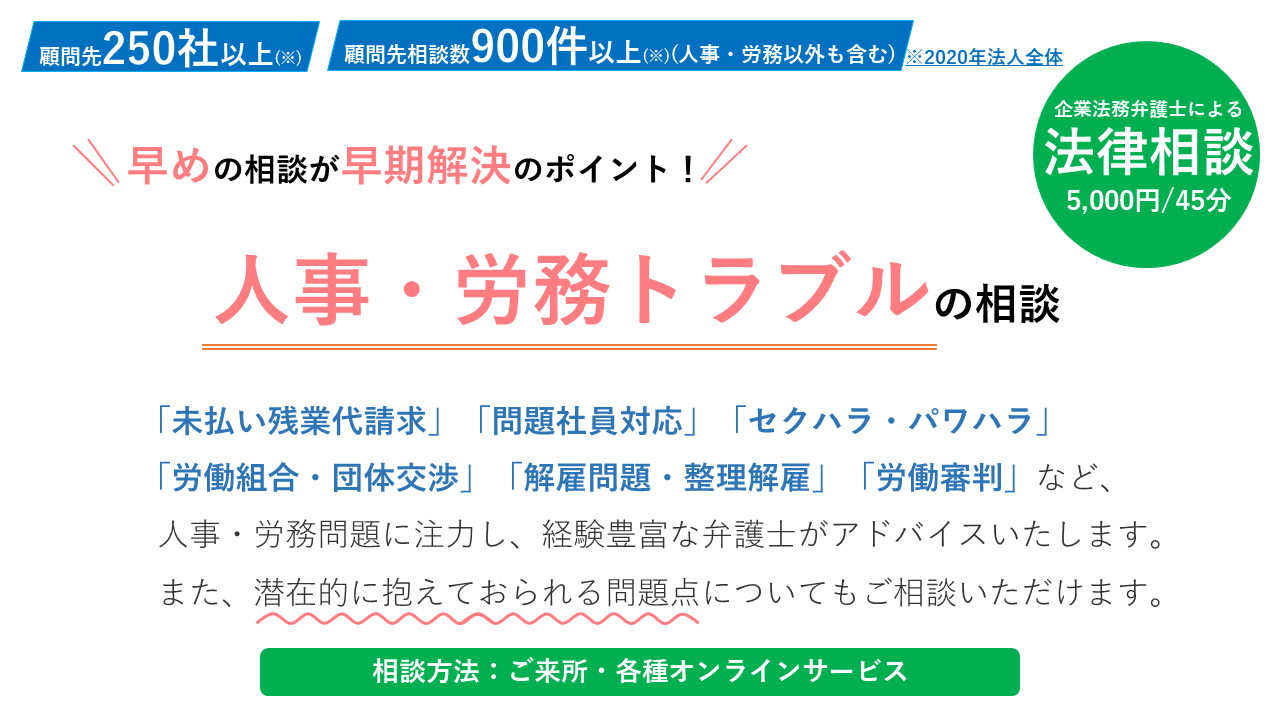
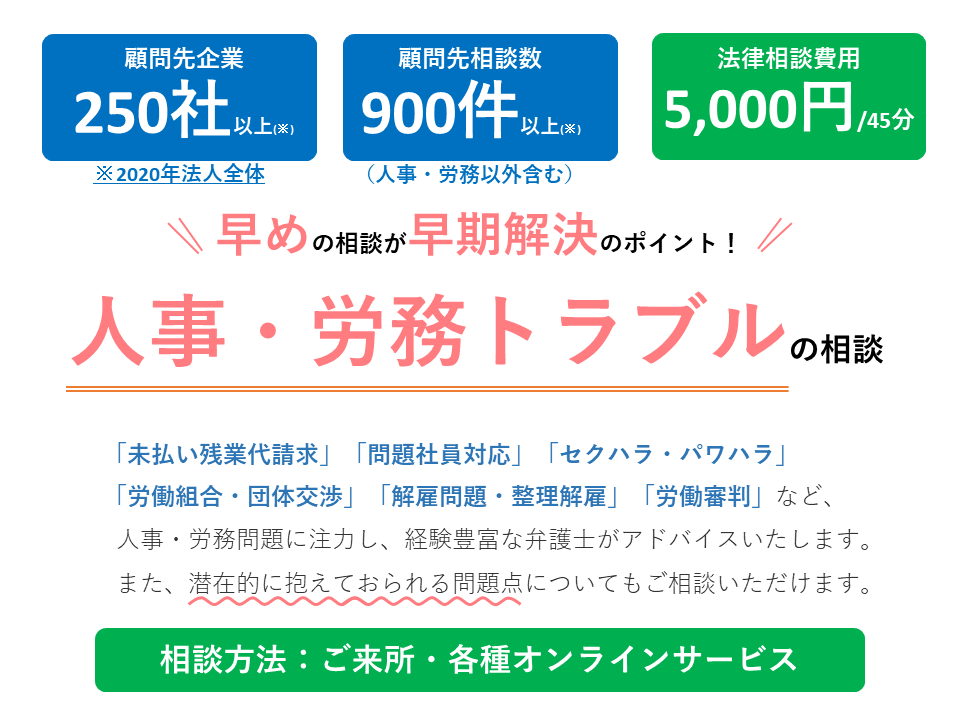
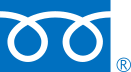 法律相談予約
法律相談予約










