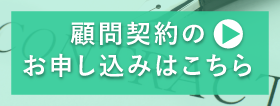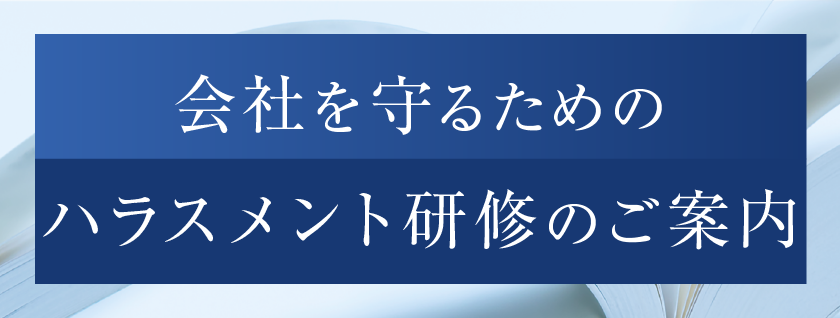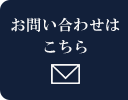売上の10%を残業手当とする賃金規定の適法性
~札幌地方裁判所令和5年3月31日判決(労働判例1302号5頁)~弁護士:薄田真司
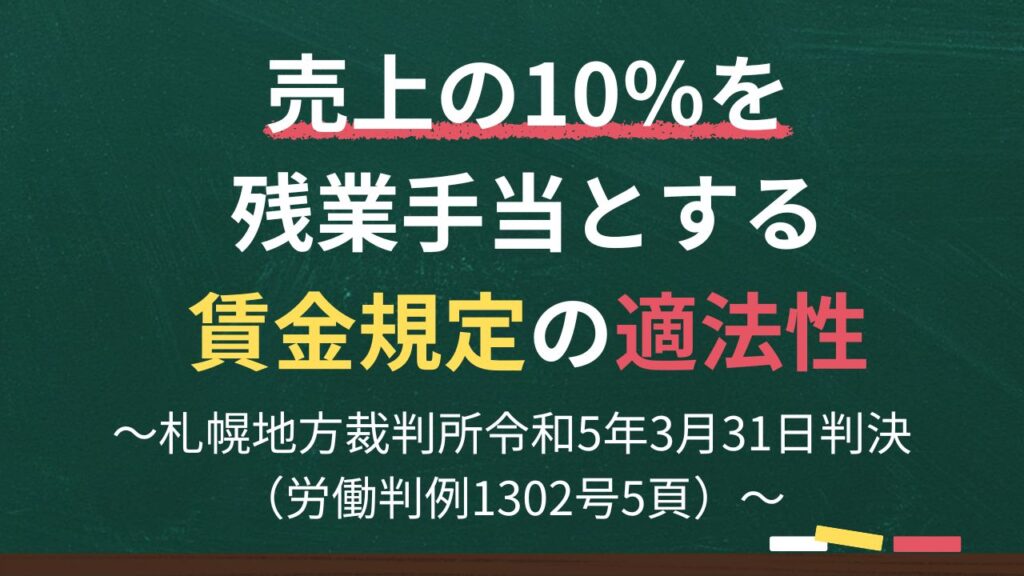
事案の概要
当事者
Y社は、一般貨物自動車運送事業を業とする株式会社である。
Xは、Y社との間で無期雇用契約を締結し、大型車両の運転業務に従事していたが、退職した者である。
賃金規定の内容
Y 社の賃金規程( 以下「本件賃金規程」という。)では、賃金構成は①基本給、②安全皆勤手当、③残業手当、④管理手当、⑤営業手当、⑥通勤手当、⑦その他となっており、③の残業手当は、基本給+諸手当に一定の率及び労働時間を乗じたものとされていた。
例えば、時間外労働割増賃金として、「(基本給+諸手当)÷1か月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間」との記載がある。
Xの雇用契約書の記載内容
Xが署名押印した雇用契約書の給与の欄には、基本給月額15万7500円と記載されているが、各種手当欄に具体的な金額の記載はなく、当社規定により支給される旨の注意書のみが記載されていた。
残業手当の支給実態
本州便の運転手に対しては、基本給(15万7500円)を支給し、売上の10%に相当する額を残業手当(以下「本件残業手当」という。)として支払っており、本件賃金規定とは異なる扱いがなされていた。
訴訟の内容
Xは、Y社に対し、未払賃金1200万円余り及びこれに対する退職日翌日である平成30年9月1日から支払済みまで年14.6%の遅延損害金を請求する訴訟を提起した。
Xは、平成28年9月1日から平成30年8月30日までの約2年間、残業代が一切支払われていないとして上記未払賃金額を算定して請求した。
本件の争点
本件の争点は、実際に支給されていた残業手当が残業代の支払として効力を有するかどうかである。
裁判所の判断
裁判所は、まず、実際に割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法第37条等に定められた割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるが、その前提として、通常の労働時間の賃金に相当する部分と残業代に相当する部分の判別可能性を要するとした。
そのうえで、使用者が特定の手当の支払によって割増賃金を支払ったと主張している場合、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するが、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、労働基準法第37条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置づけ等にも留意して検討しなければならないとした。
これを本件残業手当について検討すると、形式的には通常の労働時間の賃金に当たる部分と区別されており、又、その名称からも時間外労働等の対価とする意図で支払われていたと推認できるとした。
しかし、雇用契約書に時間外労働等の対価として支給する旨や算定方法の記載がないこと、本件賃金規定に規定されている算出方法と全く異なるものであること、採用面接やその後の賃金支給の際にも説明がない等から、本件残業手当を時間外労働等に対する対価として支払う旨の合意があったと直ちに推認できないとした。
また、本件残業手当は、労働時間の長短に関わらず一定額の支払いが行われるものであり、本件残業手当として支給される金額の中には、通常の労働時間によって得られる売上によって算定される部分と時間外労働等によって得られた売上によって算定される部分が含まれており、両者の区別ができないとした。
他方で、本件残業手当は、労働者の時間外労働時間の有無や程度を把握せずとも算定可能であり、時間外労働等を抑制しようとする労働基準法第37条の趣旨に反するものとした。
以上より、本件残業手当は、残業代の支払としての効力はなく、残業代の算定基礎となる賃金に加算されるべきと判断した。
本件のポイント
会社側からすると、本件残業手当は、その金額の算定方法が売上の10%となっているだけであり、残業手当として支払ったのだから、残業代の請求額から控除されてしかるべきと考えるでしょう。
しかし、裁判所は、本件残業手当が雇用契約書や賃金規定に規定されていないこと、採用面接等で内容の説明がされていなかったこと、残業時間の長短に関わらず一定額の支払が予定されていたこと等からして、「本件残業手当」が本当に残業の対価として支払われたものなのか(そうではなく、例えば低額である給与を底上げする一種の調整給として支払われたものではないか等)を慎重に吟味し、結論として、残業代の支払としての効力を否定しました。
その顛末として、会社は、残業代を一切支払っていなかったと判断され、さらには本件残業手当を算定基礎に加えた未払残業代を支払うことになりました。
時間外労働の対価としての残業手当を支給するのであれば、規定内容を整え、手当の内容を従業員に周知する必要があります。
また、残業手当の算定方法が時間外労働を抑制するものとする必要があります。
例えば、15時間分の残業代を固定残業代として毎月支給する例では、毎月の残業時間が15時間を超過していないか都度会社がチェックする必要が生じ、残業が抑制されると思われます。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2024年6月5日号(vol.293)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- 非管理職への降格に伴う賃金減額が
無効とされた事例
~東京地裁令和5年6 月9日判決(労働判例1306 号42 頁)~(弁護士:五十嵐亮) - 売上の10%を残業手当とする賃金規定の適法性
~札幌地方裁判所令和5年3月31日判決(労働判例1302号5頁)~弁護士:薄田真司 - 扶養手当の廃止及び子ども手当等の新設が有効とされた事例~山口地裁令和5年5月24日判決(労働判例1293号5頁)~弁護士:五十嵐亮
- 死亡退職の場合に支給日在籍要件の適用を認めなかった事例~松山地方裁判所判決令和4年11月2日(労働判例1294号53頁)~弁護士:薄田真司
- 育休復帰後の配置転換が違法とされた事例~東京高裁令和5年4月27日判決(労働判例1292号40頁)~弁護士:五十嵐亮
- 業務上横領の証拠がない!証拠の集め方とその後の対応における注意点
- 海外での社外研修費用返還請求が認められた事例~東京地裁令和4年4月20日判決(労働判例1295号73頁)~弁護士:薄田真司
- 問題社員・モンスター社員を辞めさせる方法は?対処法と解雇の法的リスクについて
- 未払残業代について代表取締役に対する賠償請求が認められた事例~名古屋高裁金沢支部令和5年2月22日判決(労働判例1294号39頁)~弁護士:五十嵐亮
- パワハラを行った管理職に対する降格処分が有効とされた事例~東京地裁令和4年4月28日判決(労働判例1291号45頁)~弁護士:五十嵐亮


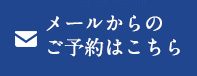

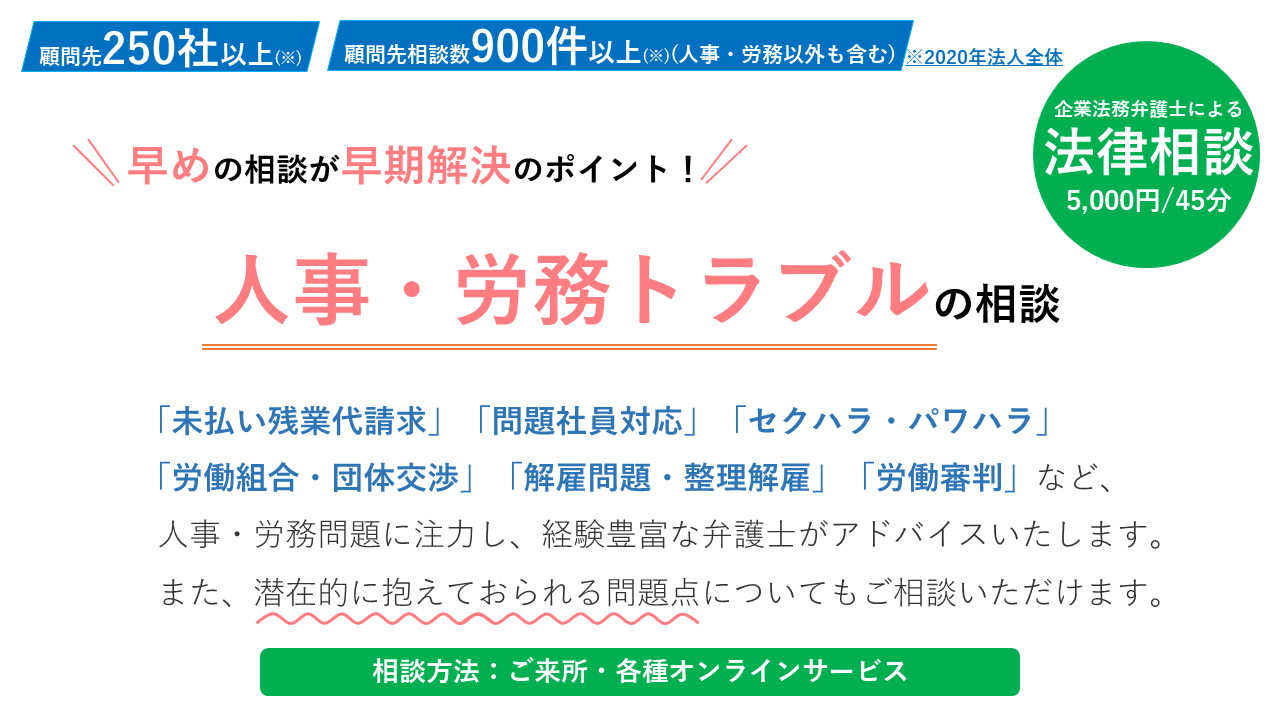
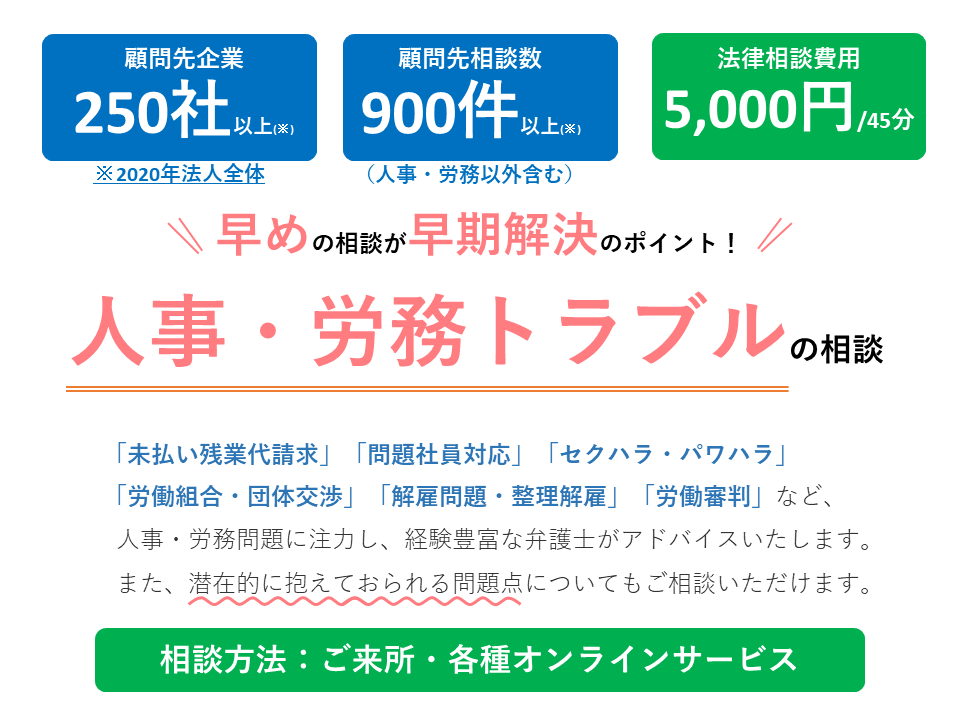
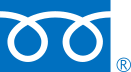 法律相談予約
法律相談予約