2025.8.21
大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
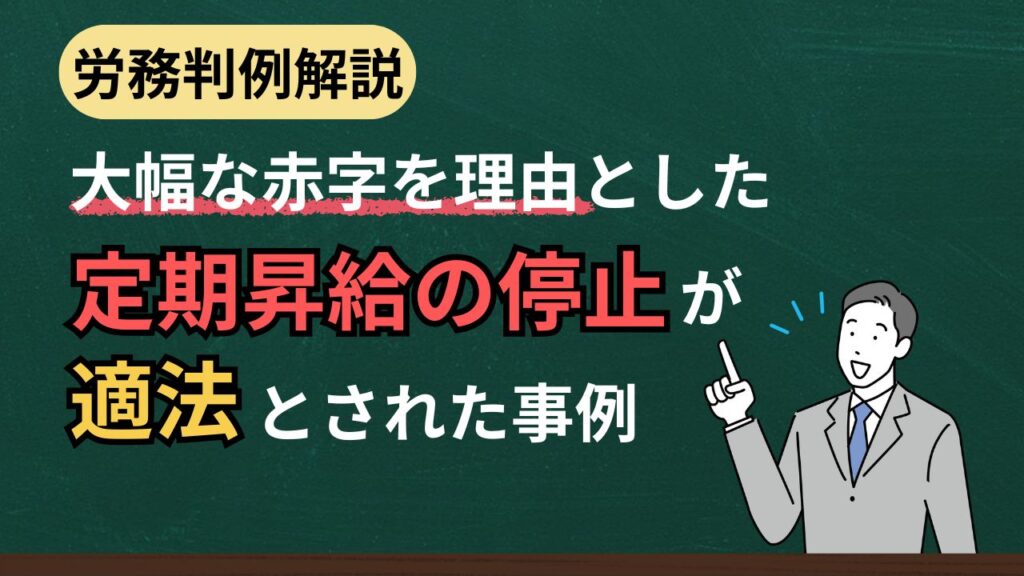
事案の概要
当事者
一審被告・被控訴人(Y法人)は、千葉県内で大学、高等学校、中学校を運営する学校法人である。
控訴人(X)は、Y法人において、平成28年から勤務している教員である。
Y法人における昇給制度
Y法人の給与規程では、昇給について、次のように定められていた。
● 第12条
昇給は基本給について行う。昇給は、定期昇給及び特別昇給とし、能力、勤務成績その他を勘案して行う。
● 第13条
定期昇給は、就職の日から1年以上経過した者について、予算の範囲内において毎年4月に行う。昇給期間は、原則として1 2か月とする。ただし、欠勤日数の多い者、勤務成績が良好でないと認められた者、○○学園懲戒規程5条2号停職又は3 号降格・降職に該当する行為があった者については定期昇給を行わないことがある。
● 第14条
特別昇給は、勤務成績が特に良好と認められた者その他特に功績があると認められた者について行う。
Y法人では、平成2 8 年度以前の少なくとも35年にわたり定期昇給が行われてきた。
また、被告において特別昇給を行う場合には、勤続10年ごとの節目に該当する教員に対し、永年勤続表彰として1号俸の特別昇給が行われてきた。
昇給廃止に至る経緯
Y法人の教職員の労働組合(本件組合)は、平成28年度の定期昇給及びベースアップ等を要求したが、Y法人は、大幅な赤字により要求どおりの回答を約束することはできない旨の返答をした。
その後団体交渉を実施したが、平成28年度の定期昇給及び特別昇給は行われず、その後、平成29年度から令和5年度の定期昇給及び特別昇給も実施されなかった(本件昇給停止)。
Xによる請求内容
Xは、Y社に対し、定期昇給は、給与規程13条によりXとY法人との労働契約の内容になっており、仮に労働契約の内容になっていなかったとしても定期昇給及び特別昇給を行うことが労使慣行となっていたとして、平成29年度から令和5年度まで、定期昇給及び特別昇給が行われた場合の賃金額と実際の賃金額の差額等の支払いを求めて提訴した。
本件の争点
主な争点は、① 毎年必ず定期昇給を行うことがXとY法人との労働契約の内容になっているか、② 定期昇給及び特別昇給を行うことが民法9 2 条により労使慣行となっていたかという点である。
裁判所の判断
争点❶について
裁判所は、以下の理由により、毎年必ず定期昇給を行うことがXとY法人との労働契約の内容になっているとは認められないと判断した。
● Y法人の給与規程では定期昇給について「予算の範囲内において」行うと定められている
● 給与規程において定期昇給の具体的内容が定められているわけではない
●本件組合とY法人との間で団体交渉を経て協約書を作成したうえで定期昇給が実施されている
争点❷について
裁判所は、一般論として、「民法92条(※)により法的拘束力のある労使慣行が成立していると認められるためには、同種の行為又は事実が一定の範囲において長期間反復継続して行われていたこと、労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないことのほか、当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることが必要であると解する」と判断した。
その上で、本件では、以下の事情を考慮して、定期昇給及び特別昇給を行うことを規範として認識していたとは認められず、労使慣行になっていたとは認められないとした。
● Y法人において財政状況を踏まえて予算を検討し、その後本件組合とY法人との団体交渉を行い、妥結した上で定期昇給や特別昇給を行ってきた
● 過去にY法人が特別昇給の中止を通達したこともあったが、本件組合からの抗議により撤回するということがあった
● 平成25年度には、平成26年度以降は定期昇給を実施できないことを否定できない旨回答していたこと
________________
※【 任意規定と異なる慣習】
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
結論
裁判所は、Xの請求を棄却した(東京高裁もほぼ同様の理由により、Xの控訴を棄却した)。
本件のポイント
本件は、給与規程に定期昇給の定めがあり、35年にわたって毎年定期昇給が行われてきたことから、定期昇給を毎年「必ず」行うということが契約内容になっていたか否かが争われたものです。
裁判所は、「予算の範囲で」という文言があったこと及び団体交渉を経て行っていたことから、定期昇給を毎年「必ず」行うことまで契約内容になっていたとは認められないと判断しました。
労使協議や人事評価等もなく漫然と長期間にわたり毎年定期昇給を行っているような場合には、定期昇給を「必ず」行うことが契約内容となっていると判断されるおそれがありますので注意が必要です。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年6月5日号(vol.304)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- タイムカード等で労働時間管理をしていない場合に概括的な認定が肯定された事例~福岡地裁令和5年6月21日判決(労働判例1332号86頁)~
- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~




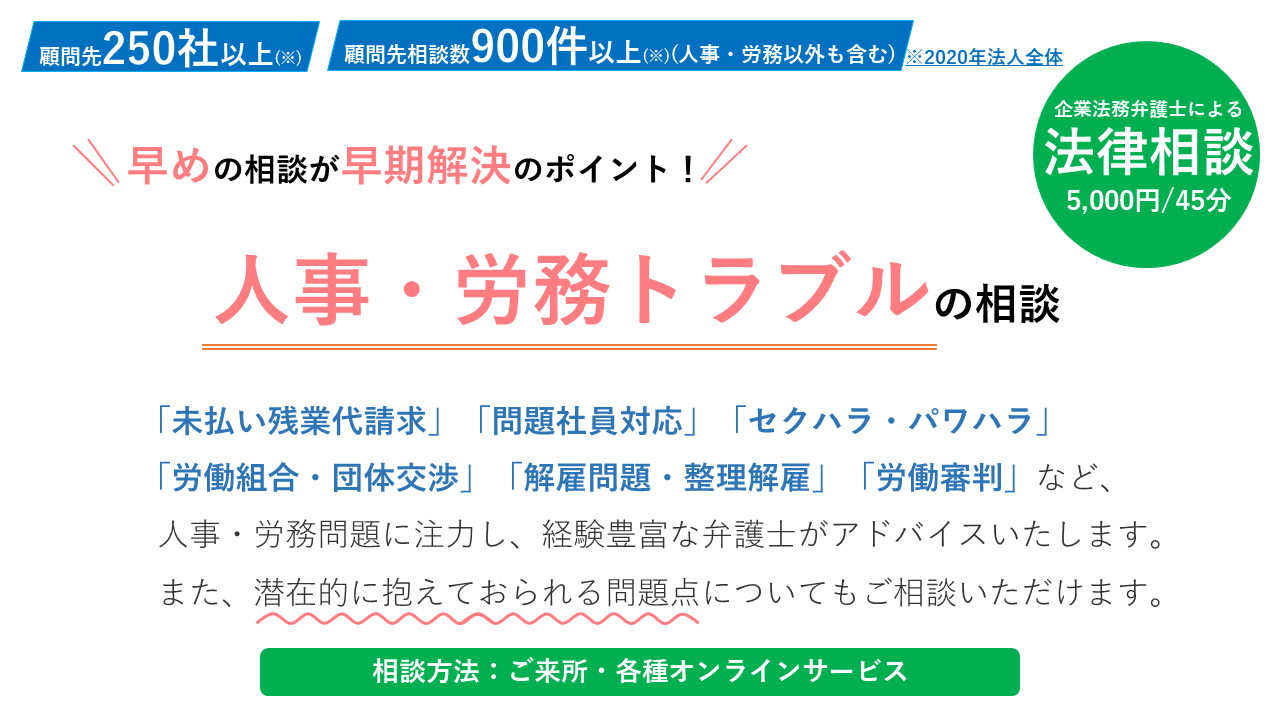
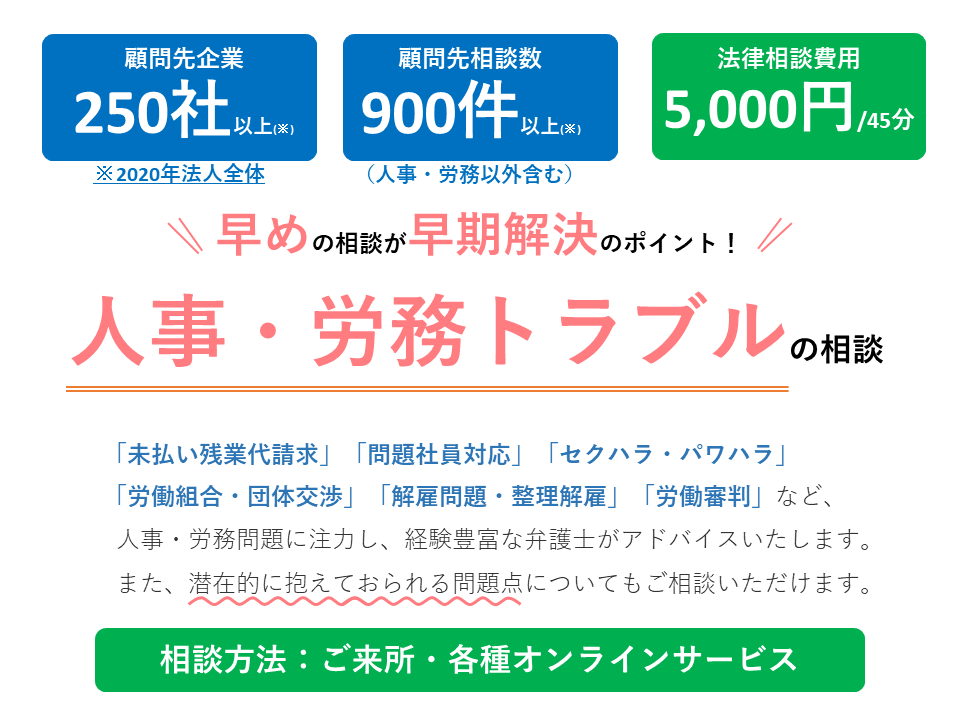
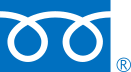 法律相談予約
法律相談予約










