2022.11.24
技能実習生に対する採用内定取消しが違法とされた事例~東京地裁令和3年9月29日判決(労働判例1261号70頁)~弁護士 五十嵐 亮
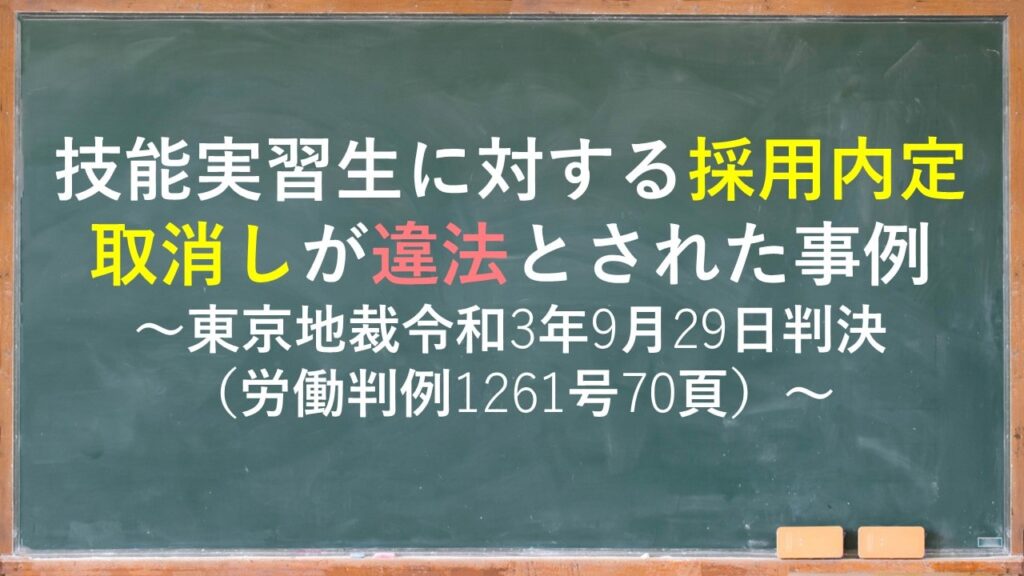
事案の概要
当事者等
被告(Y社)は、サーバーホスティング及びサーバーハウジング事業等を目的とする株式会社である。
原告15名(Xら)は、日本語学校であるA学園に在籍していたネパール人およびベトナム人の学生であり、Y社より採用内定を受けていた者である。
採用内定の経緯
Y社は、主にITインフラ事業に従事してきたが、ニアショアサービス事業への参入を検討していた。
Y社は、平成29年同事業を主たる業務とする「D LABO」を新設し、同サービスの専門家であるBに「D LABO」の運営に関するほぼ全ての権限を委ねた。
Bは、Y社の執行役員らに対して「D LABO」の事業の進捗状況や収益見込み等を報告するのみで、「D LABO」の従業員の採用を含む意思決定を独断で行っていた。
Xらは、平成29年9月頃、A学園よりY社の求人情報の紹介を受けて、順次これに応募した。
Y社は、求人票に「仕事内容」として、サーバーエンジニア(サーバーの設置・運用・保守、トラブル発生時の緊急対応等)と記載していた。
Xらは、平成29年10月6日付で、Y社より採用内定通知を受けた(本件内定)。
Xらは、本件内定を受け、Y社への入社を承諾する旨の入社承諾書及び誓約書に署名押印し、Y社へ提出した。
採用内定取消しの経緯
平成29年秋頃から、Bによる事業報告の頻度が減り、「D LABO」関連の支出が先行しているにもかかわらず一向に入金がない状態が続いていた。
平成30年2月、Bが他社の代表取締役名義の名刺を所持しているとの通報を受けたことをきっかけに社内調査をしたところ、BがY社の経費で出張を行い、他社名義で被告と競業可能性のある業務を行っていることが発覚した。
Y社が、Bに退職を促したところ、Bがこれに応じたため、平成30年2月13日、BはY社を退職した。
Bが退職したことにより、ニアショア開発事業を含む「D LABO」の事業の見通しが立たなくなった。
平成30年2月14日、Y社は、A学園に対し、Xらを予定していたプロジェクトで受け入れることが困難となったこと及びXらの仕事を確保できるよう最善を尽くす旨電話で伝えた。
平成30年2月27日、Y社は、Xらに対し、メールで、本件内定を取り消す通知を送信した(本件内定取消し)。
Xの請求内容
Xらは、本件内定取消しは違法・無効であるとして、Xらが再就職するまでの間の給与相当損害金及び慰謝料の支払いを求めて提訴したものである。
本件の争点
本件の争点は、本件内定取消しが違法かどうかという点である。
裁判所の判断
本件内定取消しは違法か?

裁判所は、採用内定の取消しは、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効となるものと解されると一般論を述べたうえで、本件については、以下の点を理由として、権利濫用として違法・無効と判断した。
・「D LABO」の事業の見通しが立たなかったのは、入社してそれほど期間の経過していないBに「D LABO」のほぼ全権を委ね、適切なマネジメント体制の構築をしないままに放置したことに由来するから、人員削減の必要性を正当化することはできない
・Y社はBが退職したわずか2週間後に本件内定取消しを行っており、真摯に内定取消しを回避する努力がされたとは認め難い
・Y社の役員らは、Xらに会ったことがなく、Xらの能力を確認するなどしていないことから、本件内定取消しに先立ってXらの能力等を踏まえた採用の可否について検討されたとはいい難い
損害として認められる範囲は?
裁判所は、給料相当損害金として、月給の6か月分を上限として損害を認めた。
加えて、本件内定を取り消されたことの慰謝料として、30万円の支払い義務があることを認めた。
本件のポイント
採用内定は、解約権を留保した労働契約が成立したと解釈されるため、採用内定取消しについても解雇権濫用法理と類似の規制に服することになります。
この点について、本件内定取消しが違法であるという結論には異論はないように思われます。
本件で特徴的な点は、採用内定取消しに対する慰謝料を認めた点です。
裁判所は、慰謝料を認めるにあたって、Xらが長年日本に留学して日本語を学んでいたこと、一般に留学生が就職先を見つけることは難しいこと、入社1か月前になって直接会っての説明もないままに内定取消しとなったことなどの事情を考慮しています。
人員削減の必要性が生じたために採用内定を取り消す必要が生じた場合には、できる限り内定取消しを回避する努力を行うことや採用内定に至った経緯について真摯に説明することなどが求められますので、注意が必要です。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2022年9月5日号(vol.272)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- タイムカード等で労働時間管理をしていない場合に概括的な認定が肯定された事例~福岡地裁令和5年6月21日判決(労働判例1332号86頁)~
- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~




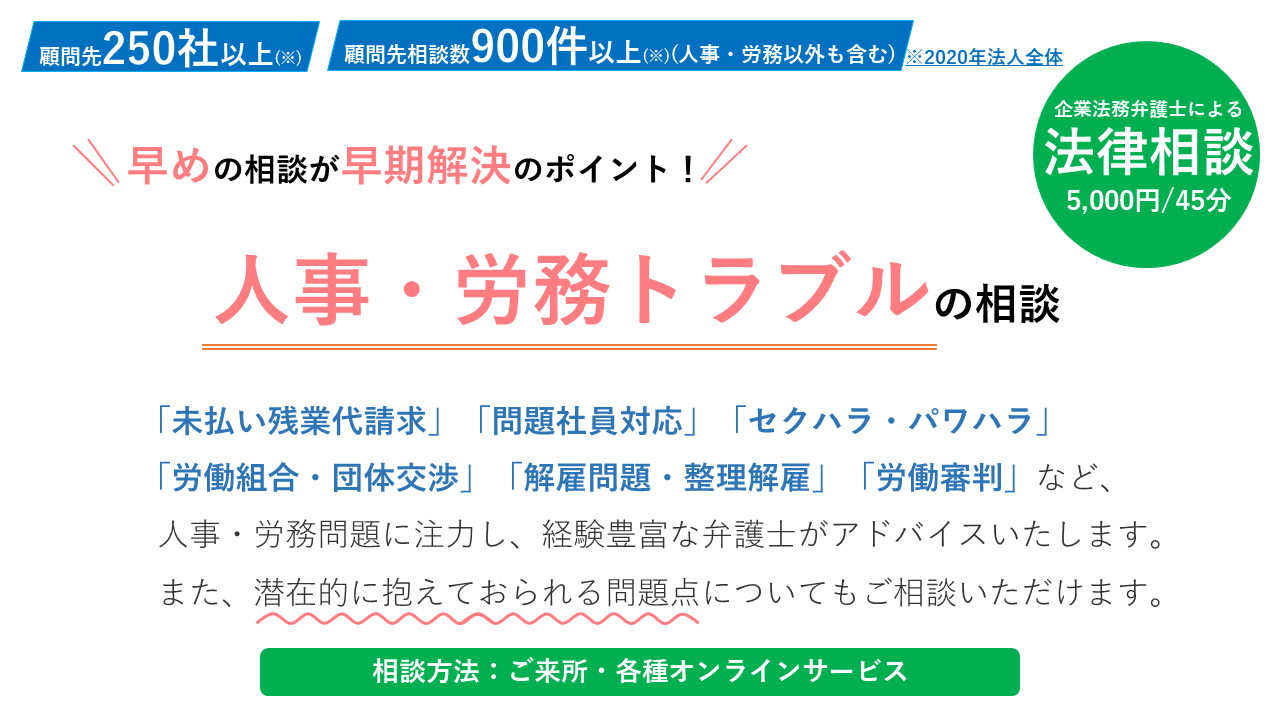
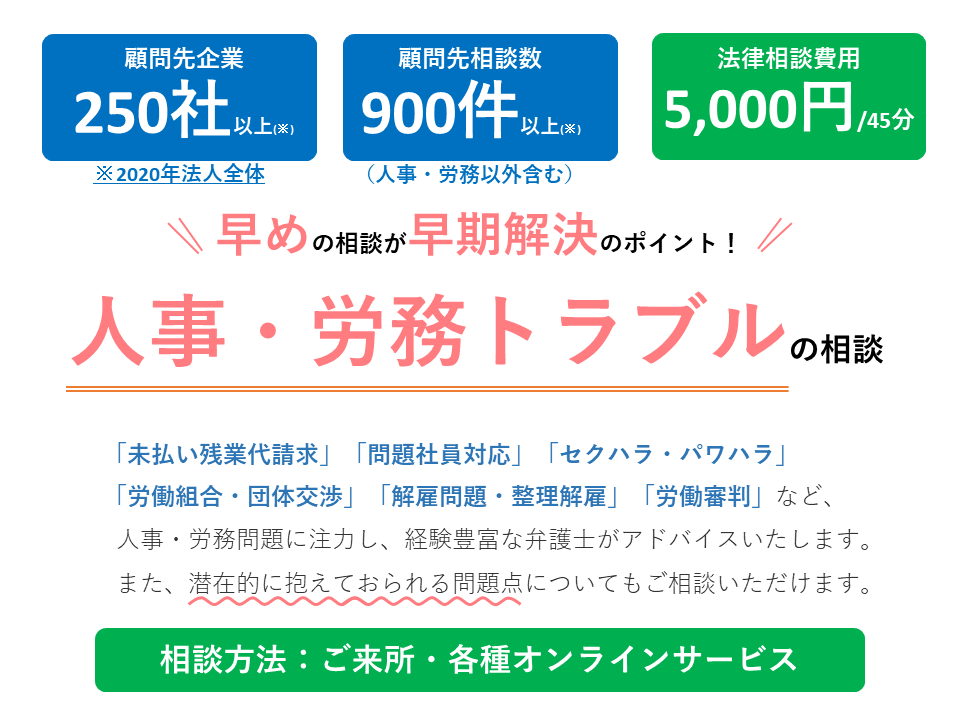
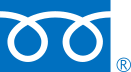 法律相談予約
法律相談予約










