2021.10.6
労働審判における口外禁止条項の適法性 ~長崎地裁令和 2 年 12 月 1日決定~(弁護士:五十嵐 亮)
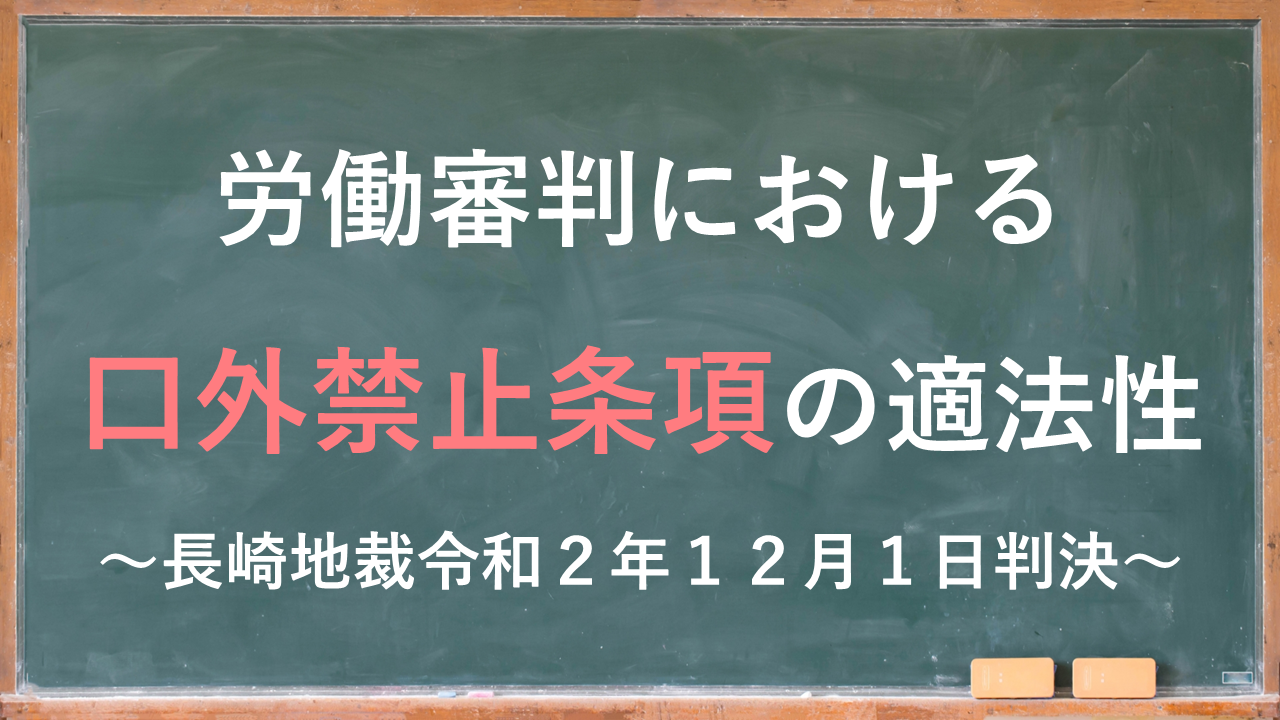
1.事案の概要
当事者
本件は、原告(X)が元勤務先の会社(A社)に対し、不当な雇止めを理由に労働審判を申し立てたところ、長崎地方裁判所が「本件に関し正当な理由なく第三者に対して口外することを禁止する」旨の条項を付した審判をしたことから、Xが、この口外禁止条項の内容が違法であるとして、国(裁判所)を被告として国家賠償請求訴訟を提起したものである。
労働審判に至った経過
XはA社との間で、平成28年4月20日から平成29年3月31日までを期間とする労働契約を締結し、主にバスの運転手として勤務していた。
A社は、契約期間満了後は、Xとの労働契約を更新しないとした。
これに対し、Xは、A社を相手方として、長崎地方裁判所に、労働者としての地位確認を求める労働審判を申し立てた。
労働審判の経過
平成30年1月12日に、第1回労働審判期日が長崎地方裁判所において開かれ、X及びA社に対する審尋が行われた。
その後、裁判官が、A社に対し、解決金として230万円を支払うことを打診したところ、A社は金額には応じられるが、口外禁止条項(本調停条項の内容の一切を正当な理由のない限り第三者に対し口外しないことを約束する)旨の
条項を設けることを要望した。
平成30年2月8日には、第2回労働審判期日が開かれ、調停成立の余地があるか協議が実施された。
XもA社も解決金の内容については応じられるが、口外禁止条項の対象範囲について、双方の意見が分かれた。
Xは、労働審判の申立てについて相談していた市議会議員(B議員)及び労働組合(C組合)のほか、労働審判に協力してくれた同僚についても解決したことを報告したいと考えていた。
これに対し、A社としては、B議員及びC組合については口外禁止条項の対象外とすることはやむを得ないとしても、同僚については対象外とすることは応じられないとした。
長崎地裁は、口外禁止条項の対象範囲について調整ができなかったため、審判(本件審判)をした。
本件審判に付された口外禁止条項(件口外禁止条項)は以下のとおりである。
| 申立人と相手方は、本件に関し、正当な理由のない限り、第三者に対して口外しないことを約束する。 ただし、申立人は、申立人が本件に関する相談を行ったB議員及びC組合に限り、本件が審判により終了したことのみを口外することができる。 |
本件の争点
Xは、本件審判における口外禁止条項は、労働審判法20条1項及び2項 に違反するとして、国に対し国家賠償請求訴訟を提起した。
本件の争点は、本件口外禁止条項が労働審判法20条1項及び2項に違反するか否かという点である。
2.裁判所の判断

裁判所は、当事者間の紛争の経過及び結果について、会社関係者等の第三者に口外されることで、不正確な情報が伝わることにより、当事者が無用な紛争に巻き込まれることがあり得るところ、口外禁止条項は、このような事態に陥ることを未然に防ぐという側面を有しており、紛争の実情に即した解決に資するといえるから、一定の合理性を見出すことができるとし、口外禁止条項を付すること自体については、直ちに違法になるわけではないとした。
もっとも、本件審判における口外禁止条項については、B議員及びC組合に対しては、審判で終了したことのみを口外でき、その他の者に対しては、審判で終了したことさえも口外できない内容であることからすれば、過大な内容であるといわざるを得ないという旨判断し、結論として、本件口外禁止条項は労働審判法20条1項及び2項に違反し違法であると判断した。
3.本件のポイント
実務上、労働紛争を合意により解決する際には、使用者側としては、他の労働者への紛争の波及を防止するために口外禁止条項を設けるということが多く行われています。
特に残業代請求などにおいては、他の労働者に波及すると第二第三の請求をされることがあ
るため、使用者側からすれば、重要な条項となります。
本判決は、あくまでも「労働審判」の場合に無限定に口外禁止条項を付することが違法になる場合があるという判断ですので、調停や和解等において口外禁止の合意をする場合にまで違法となるわけではないことについては注意が必要でしょう。
<※1>
【労働審判法】第20条
1. 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。
2. 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2021年8月5日号(vol.259)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~
- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~




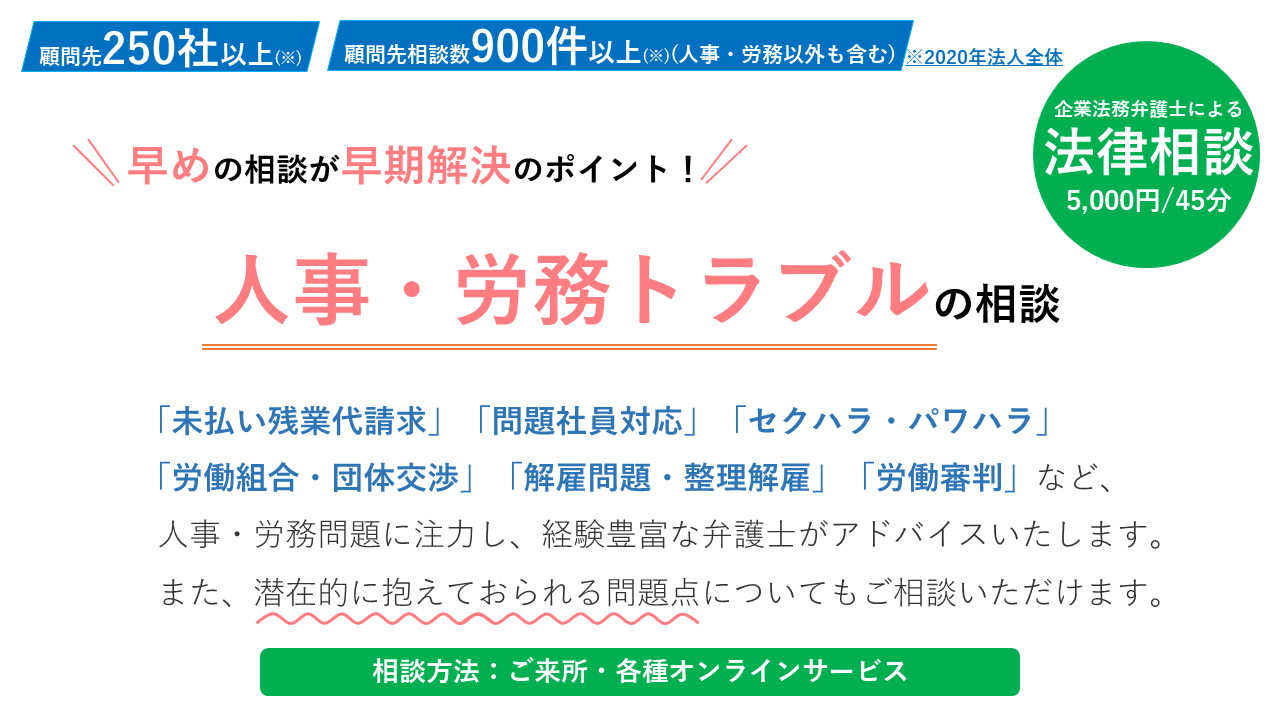
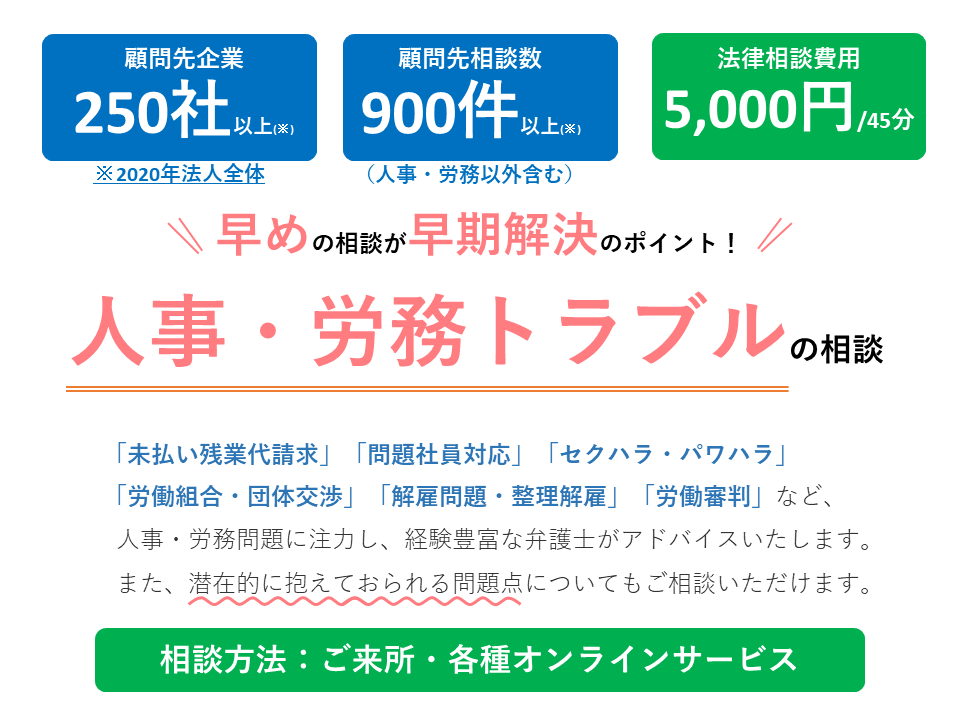
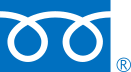 法律相談予約
法律相談予約










