2025.11.12
【弁護士が解説】建設業法の基本

1.建設業法の基礎と許可制度
建設業を営むなら避けて通れない「建設業法」です。
第1章では、許可制度の基本をやさしく解説し、スムーズな事業運営の第一歩をサポートします。
建設業法の目的
建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること、また建設業の健全な発展を図ることを目的としています。
この法律によって建設業界の信頼性が保たれ、安全な社会インフラの整備にもつながっています。
許可制度の基本:建設業を営むなら許可が必要?
原則として、1件あたり500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うには、建設業の許可が必要です(法3条)。
許可を受けていない事業者がこれらの工事を行えば、違法行為となり、罰則の対象となる可能性があります。建設業は29業種に分類されており、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
許可取得のための要件
許可を取得するためには、次のような要件を充たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること(建設業における経営経験(5年以上など)が必要です。)
② 専任技術者がいること(建築士や施工管理技士、または、実務経験が一定年数ある技術者の常勤配置が求められます。)
③ 財産的基礎があること(自己資本、資金調達能力など、経営の安定性が審査されます。)
④ 欠格要件に該当しないこと(過去に法令違反があった場合や暴力団関係者などは許可が下りません。)
⑤ 誠実な業務遂行体制があること
これらの要件を充たした上で、都道府県知事または国土交通大臣あてに申請書類を提出します。
申請区分や必要書類は細かく定められているため、詳しくは専門家にご相談されることをおすすめします。
許可後の注意点
建設業の許可は「許可を取得したら終わり」ではありません。
以下のような運用上の注意点が重要です。
建設業許可は5年ごとに更新申請が必要で、忘れると無許可営業扱いになる可能性があります。
また、役員変更や事務所移転など事業内容に変更があれば届出が必要です。
また、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が必要です。
忘れると行政処分の対象となることもあります。
許可制度のまとめ
建設業法は、現場だけでなく経営にも密接に関わる重要な法律です。
特に許可制度の理解は、営業範囲の把握やリスク管理にも直結します。
法令を正しく理解し、事業に活かしていきましょう。
2.建設業法違反と実務の落とし穴
次に、建設業法違反につながる代表的な行為とその罰則、実務で注意すべきポイントについて
解説します。
よくある違法行為
建設業法で禁止されている行為は多岐にわたりますが、特に注意が必要なケースを紹介します。
⑴ 無許可営業
許可が必要な工事を、許可を持たずに請け負うことは、行政処分(建設業法第28条第1項第6号)
や刑事罰(同法第47条第1号)の対象となります。
建設業許可は5年ごとの更新が必要であり、更新を怠ったまま建設工事を請け負うと、無許可
営業とされるため、十分な注意が必要です。
⑵ 名義貸し
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者と専任技術者という人的要件を満たす必要があります(コモンズ通心204号)。
人材確保の手段として、経験者を取締役や技術者として迎えることもありますが、許可取得後も常勤として勤務している必要があります。
常勤実態がない場合は、人的要件を欠くことになるため、行政処分の対象になります。
また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります(法29条1項5号、29条の4)。
これが、いわゆる建設業許可の「名義貸し」の問題です。
⑶ 契約書等の作成
建設業法では、適正な契約書(第19条)や見積書(第20条)の作成が義務付けられています。
これらを交わさないこと自体が即座に行政処分の対象になるわけではありませんが、契約内容の明確化は、将来の紛争防止のためにも不可欠です。
違反した場合のリスクと罰則
上記の違法行為のほか、役員による刑法違反(例:贈収賄)や労働法令違反も、建設業法上の行政処分対象となります(第28条第1項第3号)。
建設業法に違反すると、指示処分や営業停止、許可取消といった行政処分や刑事罰の対象になります。特に公共工事では、処分歴があると入札に参加できないこともあり、経営に大きな影響を及ぼします。悪意がなくても違反となるケースも多く、現場と経営の両面での意識共有が欠かせません。
コンプライアンスを強化するために
法令違反を防ぐには、社内研修の実施や書類管理の徹底、顧問専門家との連携体制の構築など、日常業務の中で継続的に法令遵守を意識する仕組みが重要です。
現場任せにせず、会社全体でコンプライアンスを根づかせる姿勢が求められます。
建設業法は、違反すれば罰則のある「制限」ですが、遵守することによって、取引先や顧客からの信頼を得るものにもなります。
社会的信頼の確保と安定経営のためにも、法令を味方につける姿勢が重要です。
コンプライアンス体制を整え、リスクを回避できる組織づくりを目指しましょう。
3.一括下請負の禁止について
建設業法における「一括下請の禁止」とは
建設業法第22条では、元請業者が請け負った建設工事を「一括して他人に請け負わせる」こと、いわゆる「一括下請負の禁止」を規定しています。
これは、施工の品質や安全性を確保するため、元請が工事に直接関与し、責任を持って遂行することを義務付ける趣旨によるものです。
元請が自ら工事を行わず、「実質的に関与」していないと判断されるケースでは、一括下請負とみなされます。この「実質的に関与」とは、元請が自ら施工計画の作成、工程・品質・安全管理、技術的指導等を実施していることをいいます。
一括下請負となる具体例
(1)請け負った建設工事の全部を一括して他の業者に請け負わせる場合
A社が2棟の住宅建築工事を請け負い、それぞれの棟をB社とC社に下請負させ、自社では一切施工を行わなかった場合です。
この場合、元請としての施工の実質的な関与がないと判断され、一括下請負と判断される可能性があります。
(2)請け負った建設工事の主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
A社が、建築一式工事を請け負い、自社は付帯工事である電気工事のみを施工し、本体工事を建築専門のB社に一括して下請負させる場合です。
このように、発注者との契約が建築一式工事であるにもかかわらず、自社では主要でない一部のみを施工している場合、請負者として実質的な関与がないと判断され、一括下請負と判断される可能性があります。
(3)一部の工事でも、それが独立性のある工事である場合
A社が2kmの道路改修工事を受注し、1kmを自社施工、残り1kmをB社に全て下請負させた場合です。
このように一部でも、それ自体が独立して一件の工事として成立する内容であれば、その部分について一括下請負と見なされる可能性があります。
一括下請の禁止の例外
例外として、民間工事(共同住宅の新築を除く)の場合は、発注者から事前に書面による承諾を得ていれば、一括下請負は認められています。
発注者との合意内容を明確にし、適切な書面を残すことが必要です。
一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分
一括下請負は、発注者からの信頼を損なう重大な行為と位置付けられており、違反があった場合には建設業法に基づく監督処分等が科されます。
国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」をみると、「処分理由:一括下請負」に関して、毎年一定数の行政処分が行われていることがわかります。
一括請負禁止のポイント
一括下請負の禁止は、形式ではなく「元請が実質的に工事を担っているか」が重視されます。
契約や現場管理だけでなく、元請としての実行力を示す記録の保管も必要です。
違反防止には、社内体制や業務の進め方を見直し、建設業法に沿った体制を整えることが重要です。
4.経営事項審査について
ここまでは、建設業法における法令遵守の重要性について説明してきました。
ここからは、会社をワンランク上のステージに引き上げる経営事項審査(以下「経審」といいます。)について取り上げます。
建設業法における「経営事項審査」とは
経審とは、国や地方自治体などが発注する公共性のある工事(以下「公共工事」といいます。)を直接請け負うために、建設業者が必ず受けなければならない審査です(建設業法第27条の23)。
この審査では、建設業者の経営状況や技術力などが数値化され、その結果は入札参加資格の判断材料として活用されます。
つまり、経審は公共工事を受注するための入口ともいえる重要な制度です。
審査の内容と評価の仕組み
経審は、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)、完成工事高(業種別)や自己資本額、平均利益額を評価する経営規模(X点)、技術職員数や元請工事高を評価する技術力(Z点)、労働福祉環境、法令順守状況、建設業法に関する加点要素などを含むその他審査項目(W点)があります。
これらの点数をもとに「総合評定値(P点)」が算出され、発注者が入札参加資格の判断材料として活用します。
P点が高いほど、より高額・大規模な案件への入札が可能になります。
なお、P点が高ければ良いというわけではなく、中小規模の建設業者にとっては、点数が高くなった結果、大型公共工事にしか入札参加資格がなくなってしまい、かえって不利になる場合もあるという話を聞いたことがあります。
自社の事業規模や戦略に応じた評価を目指すことが重要です。
審査を有利に進めるには?
経審は一度取得すれば終わりというものではなく、原則として毎年の更新が必要です。
審査基準日(通常は事業年度の終了日)を基に、有効期間は1年7カ月の間に限られています(施行規則第18条の2)。
したがって、毎年公共工事を直接請け負うためには、有効期間が切れることのないよう、継続的に経審を受ける必要があります。
審査においてP点を改善するには、単に売上高を上げるだけでなく、技術職員の増員など多方面からの対策が求められます。
特に近年では、W点に関して新たな加点要素が追加されるなど、制度の見直しが進められました(令和4年国交省告示第827号)。
たとえば、ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況、建設機械の保有に関する状況、環境配慮に関する取組などが評価対象となっており、比較的短期間で対応できる項目も多く含まれています。
X点やZ点の向上が時間を要する一方で、W点の積み上げは戦略的に取り組みやすい分野といえるでしょう。
経営事項審査のまとめ
経審は、企業の信頼性と成長性を示す健康診断ともいえる制度です。
公共工事を受注するためにはもちろん、民間の取引先に対する信用力の証明としても活用できます。
制度を正しく理解し、自社の強みを最大限に活かすことで、建設業界における競争力向上を図っていきましょう。
[参考]
・『一括下請負の禁止について』(平成28年10月14日付国土建第275号)
・国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(https://www.mlit.go.jp/nega-inf/)
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年6月号~9月号(vol.304~vol.307)>
※本記事は、4回連載で掲載したものを再編成し掲載しております。
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。




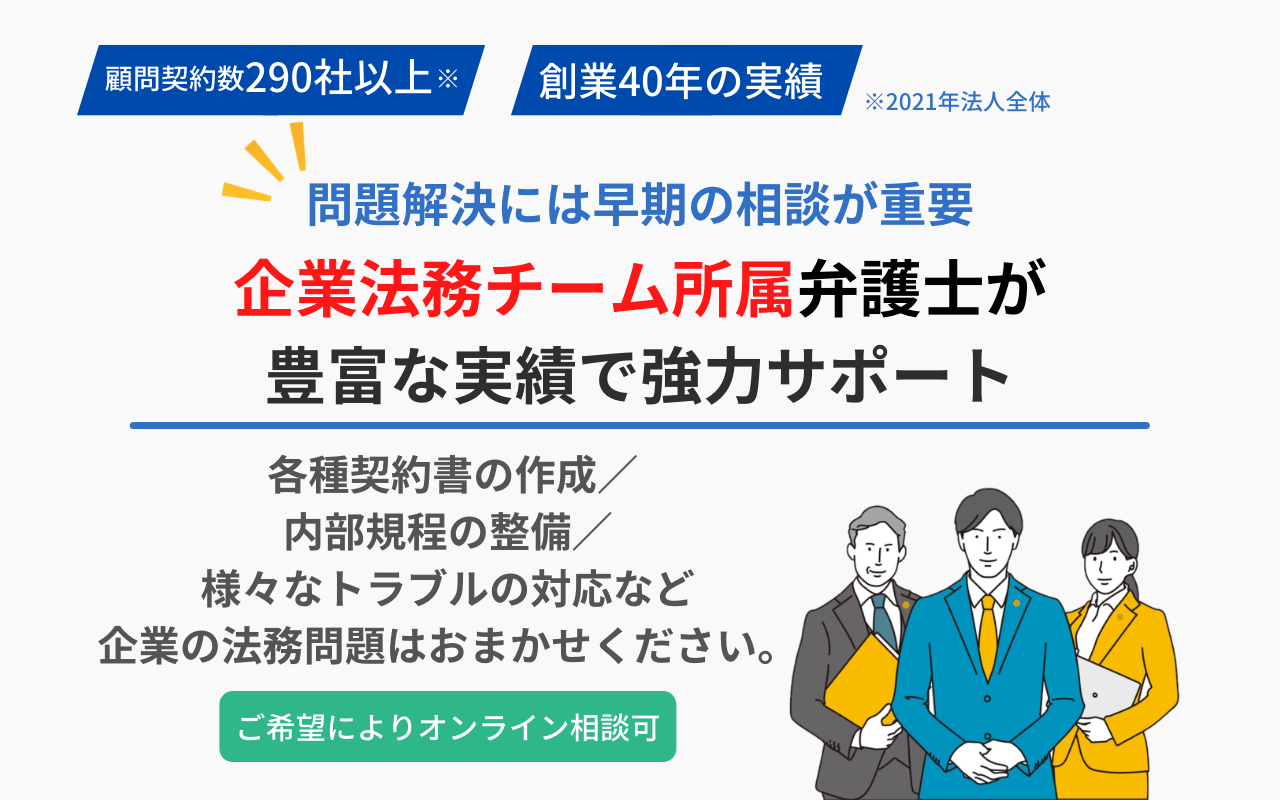
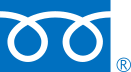 法律相談予約
法律相談予約










